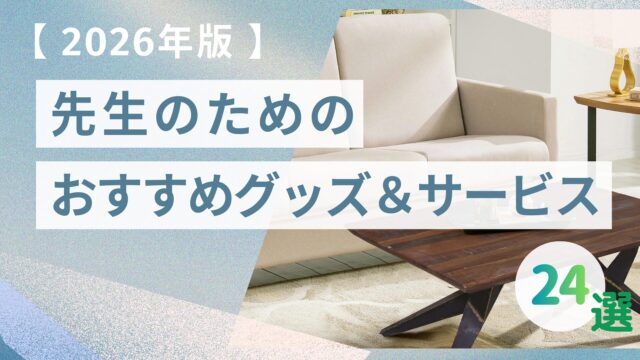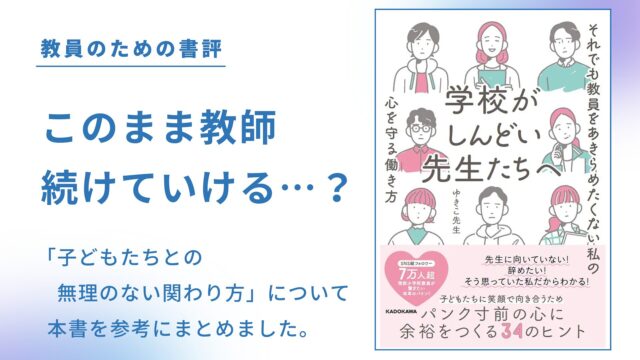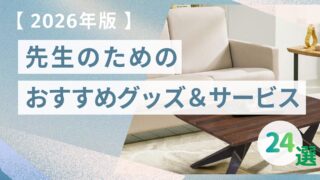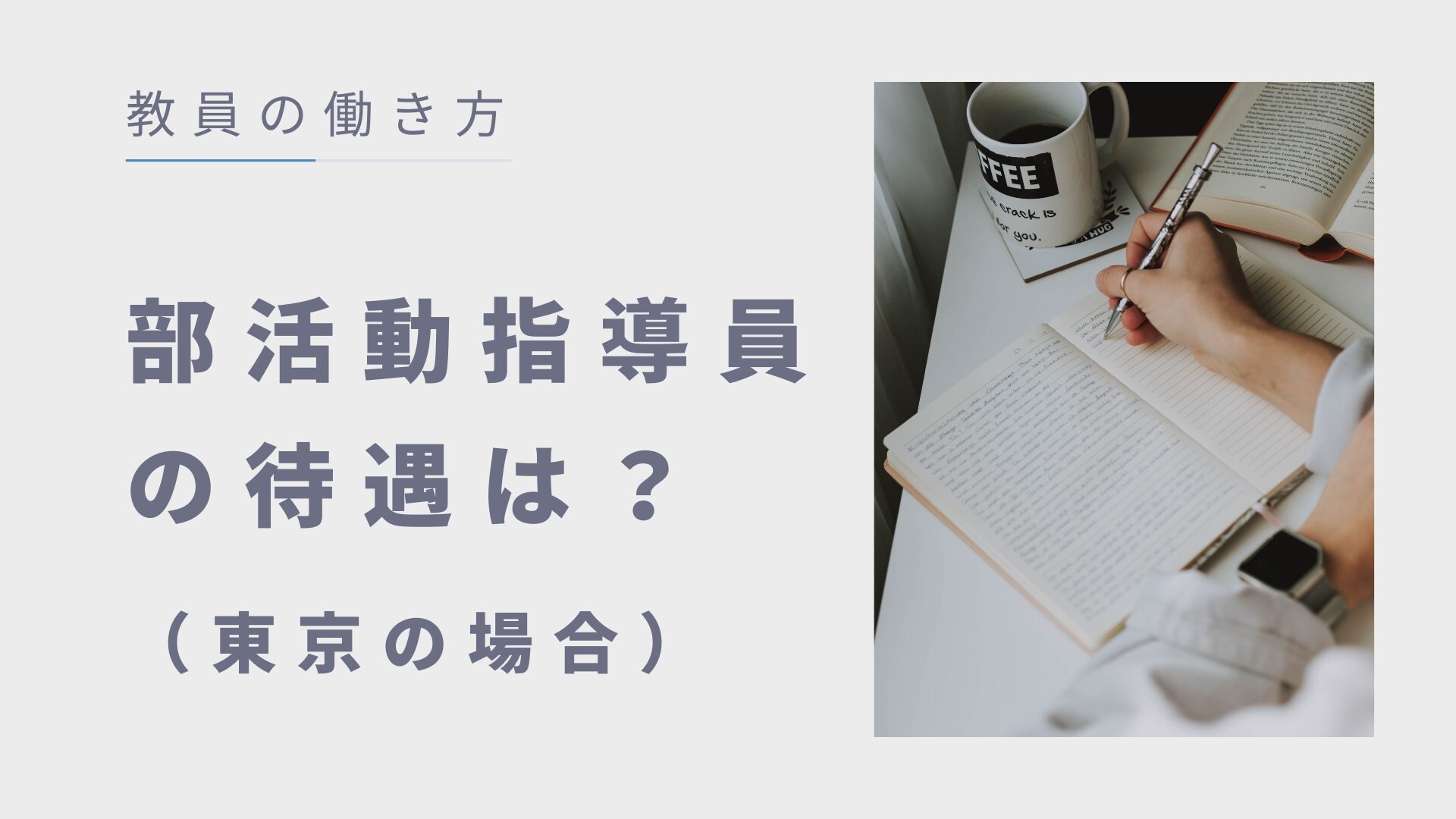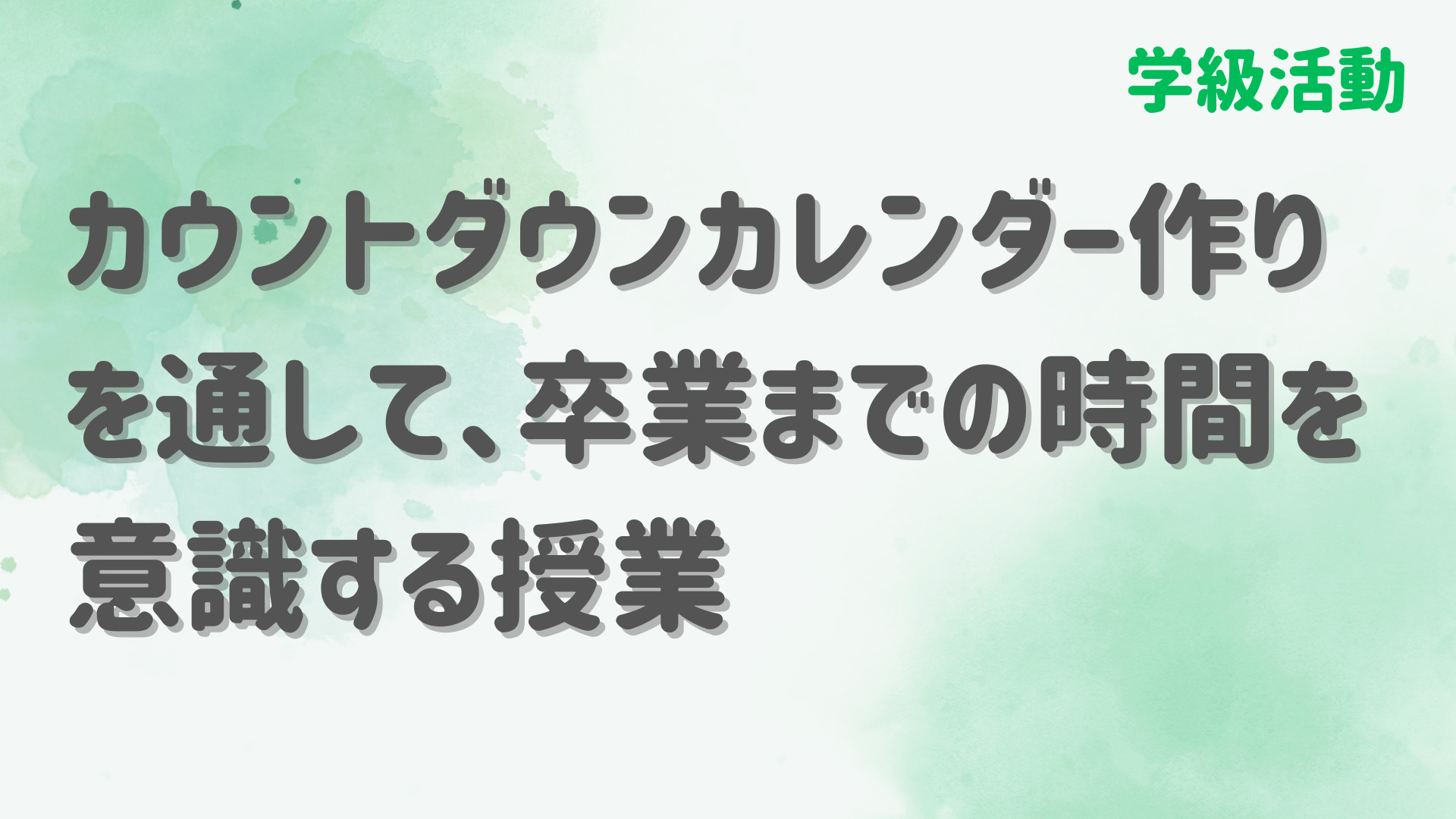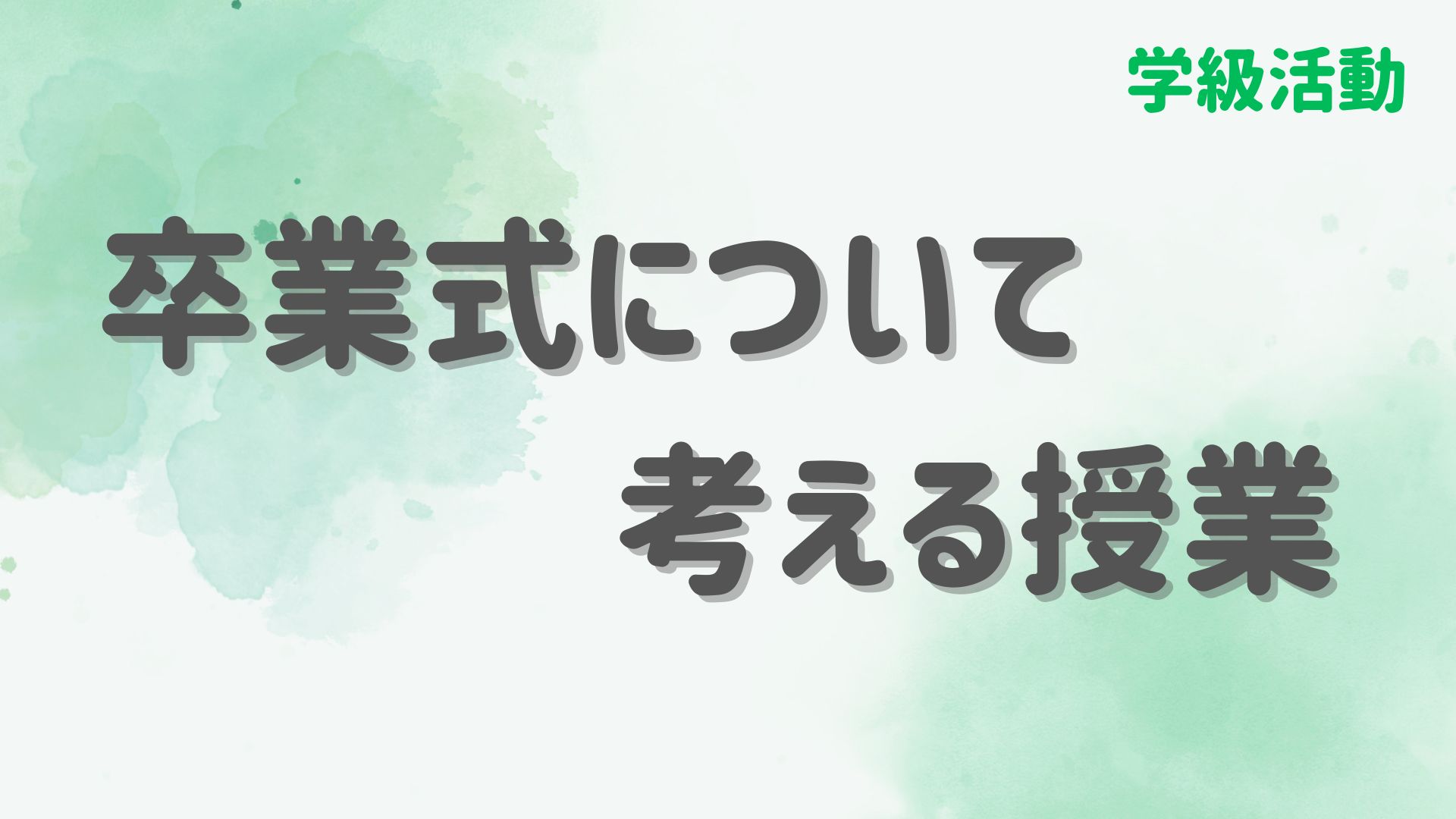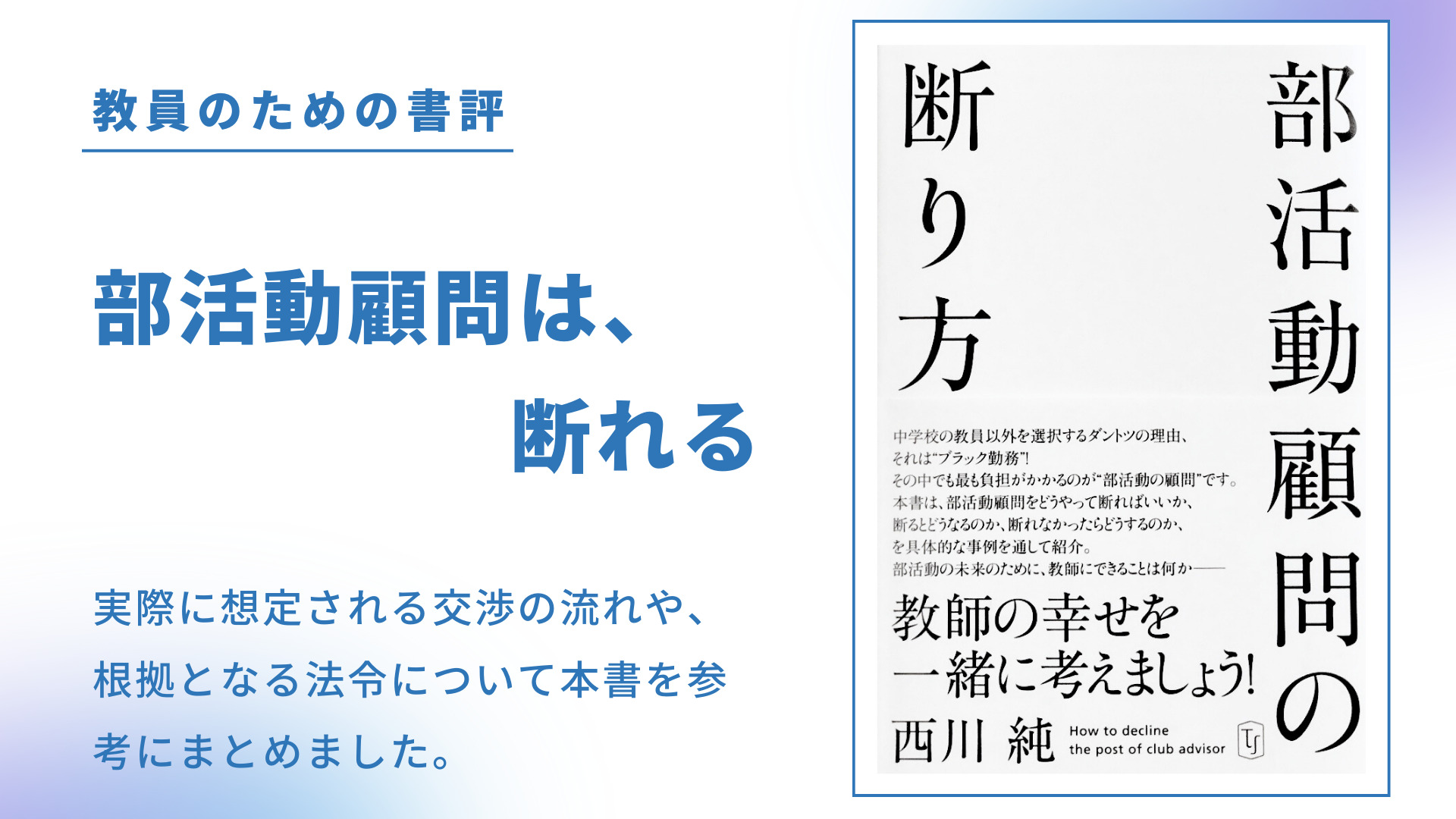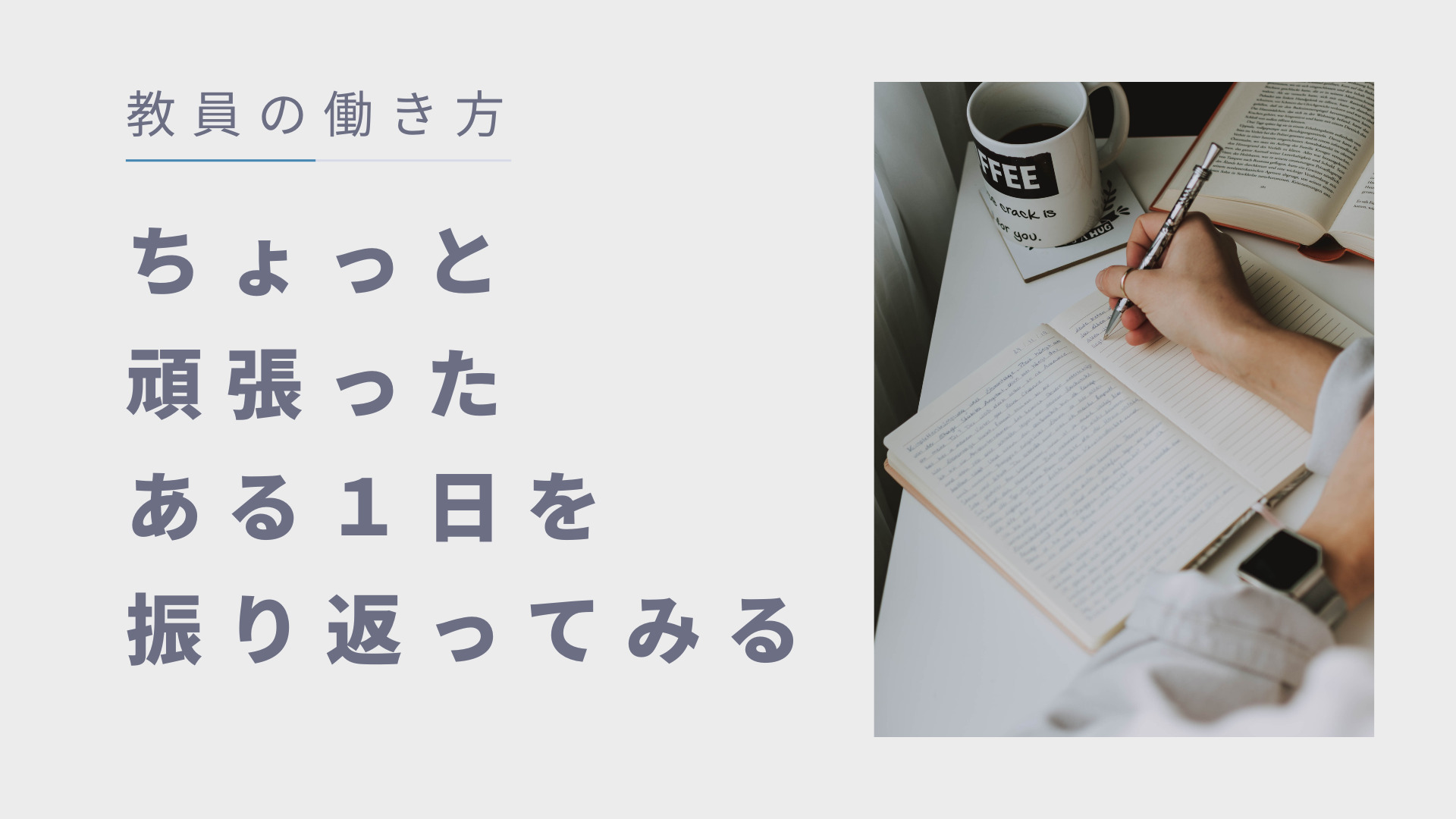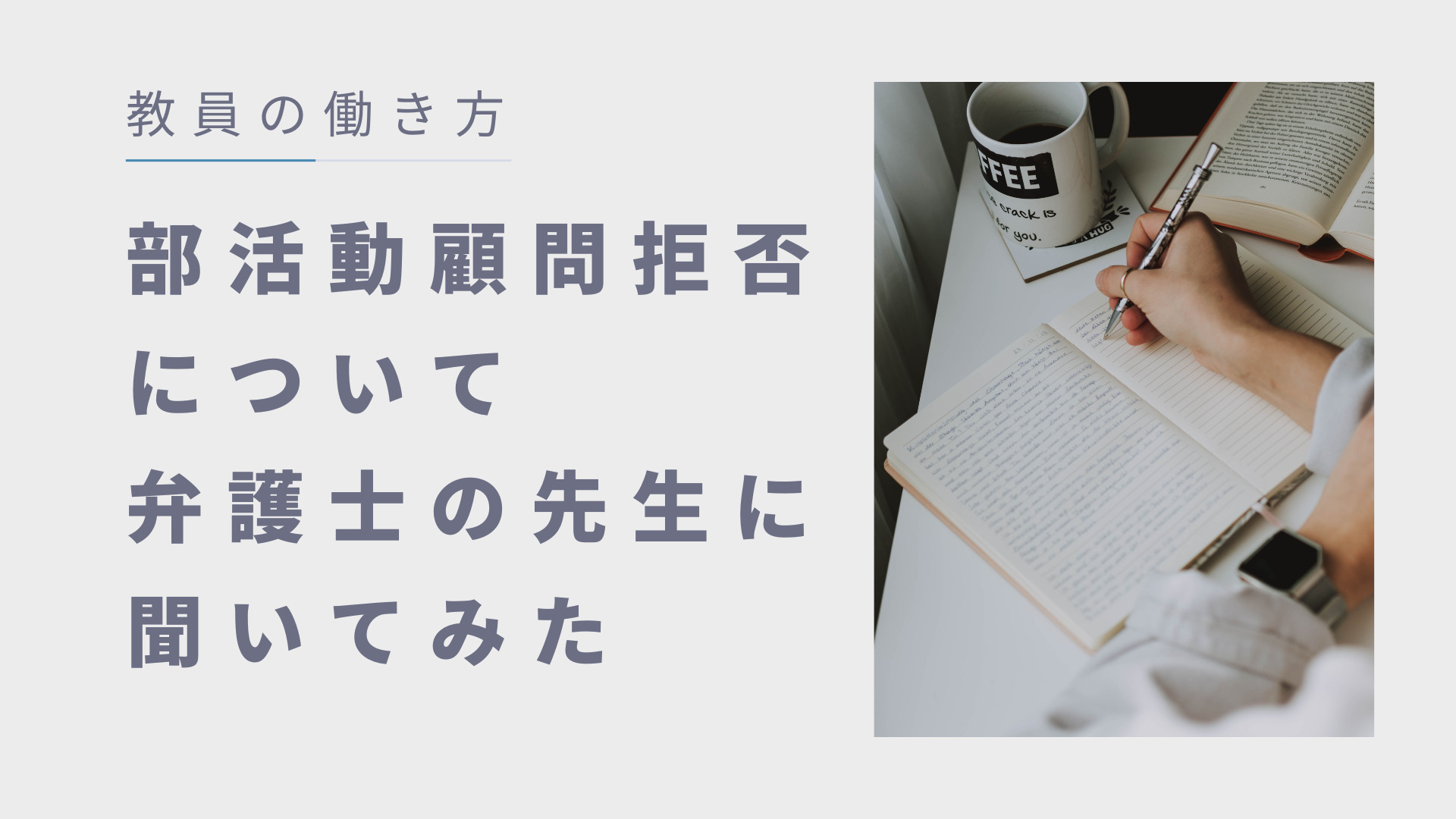保護者面談の準備とおすすめの会話の流れについて【進行+記録補助シート付き】

夏休みに入り、保護者面談を行う学校も多いと思います。
その際、初任の先生はもちろんですが、ある程度の年数を経験された先生方の中にも
- 「なかなか慣れなくて、スムーズに会話を進められない」
- 「あっという間に終わってしまって、時間を持て余してしまう」
- 「結局伝えたいことが伝えられなかった」
- 「気付けば自分だけがずっとしゃべっていた」
…など、なかなか面談を思うように進められず、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

私も最初は緊張して、ぎこちない会話になってしまうことが多かったです。
しかし、そんな私も回を重ねるにつれて徐々に進行のコツをつかみ、今では滞りなく面談を進められるようになっただけでなく、保護者の方からも
「クラスの様子がよくわかって安心した」「悩んでいたことを相談できてよかった」など、嬉しいリアクションをいただけるようになりました。
今回は初任の先生方や、保護者面談に苦手意識のある先生方を対象に、おすすめしたい面談の進行方法や実際の会話のながれ、当日までにやっておきたい準備などについて
これまでの私の実践をもとに、できるかぎり具体的にまとめてお伝えしたいと思います。

スタートからゴールまでのイメージを持てると、気持ち的にも余裕を持って面談できそうだね。

今回付録にした【進行+記録補助シート】は、面談の準備→進行→記録のすべてをサポートできるよ!
※ご紹介しますのは個人の実践に基づく見解ですので、予めご了承ください。少しでも先生方のご参考になれば幸いです。
今回の付録である【進行+記録補助シート】は、PDF資料としてページ下部にご用意しました。
ぜひダウンロードしてご活用ください。
保護者面談に対する基本的な考え方
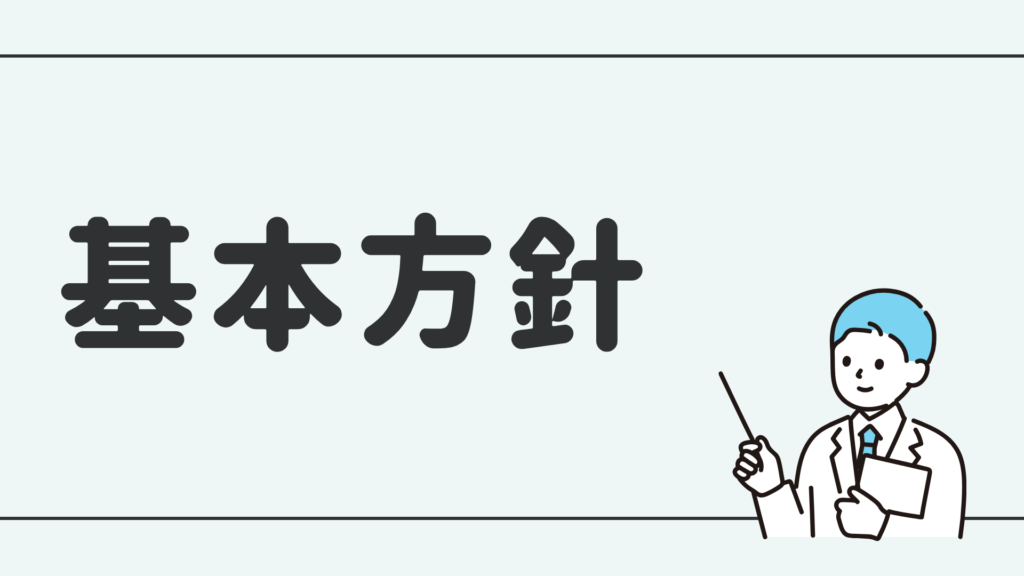
私が面談を行う際、最も意識していることは
「この面談を通して、保護者の方と良好な協力関係を築く」
ということです。
極端ではありますが、これを達成できればオールオッケー!ぐらいの気持ちで臨んでいます。
そして、その実現のためには
- 担任が生徒をよく見ている人だという印象を与えること
- 家庭での困り感を共有して一緒に考えようとする姿勢を示すこと
これらをおさえることが重要であると考え、そのための事前準備をしていきます。

あらかじめゴール(何のために面談をするのか)を決めておくことで、自分のとるべきスタンスが見えてきます。
事前準備について
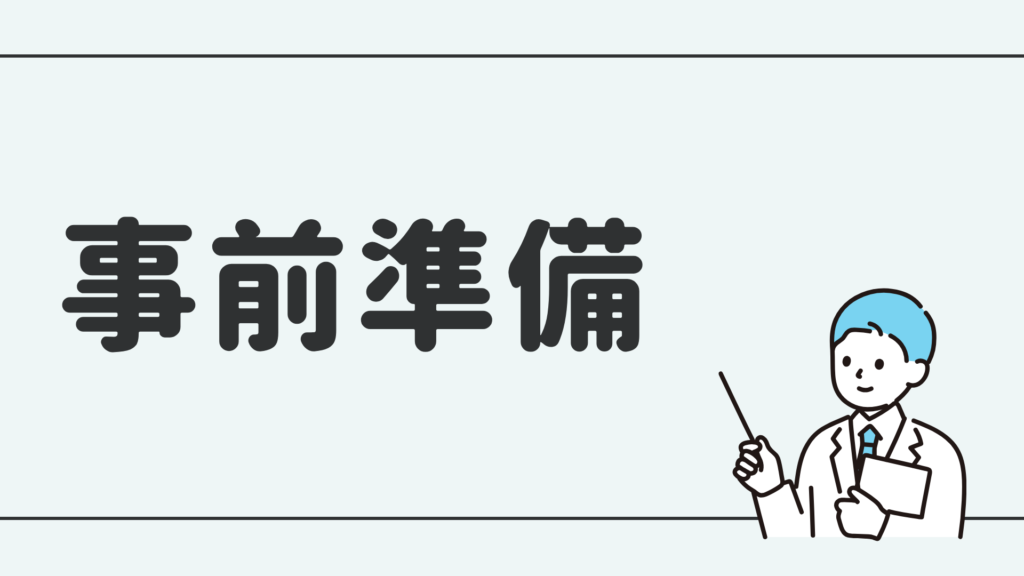
「担任が生徒をよく見ている人だという印象を与える」ための準備として、面談時に保護者の方へ伝えたいことを、生徒の学校生活の様子を振り返りながら事前にリストアップしていきます。
(ここで付録のPDF資料をお使いください)
カテゴリーとしては、
- これまでの学習・生活
- 家庭での様子
- これからの学習・生活
の3つに分けてまとめていきます。
①これまでの学習・生活
学習面ではこれまでの成績から生徒の現状を把握し、授業態度や学習計画表などから学習に対する意欲や取り組む姿勢などをまとめます。
生活面では、体調や友人関係、係活動や清掃活動に取り組む姿勢、提出物の提出状況(忘れ物の頻度)などをまとめます。

授業に来ていただいている他教科の先生や、生徒が所属するの部活動の顧問の先生などから情報収集すると、自分が見えていなかった生徒の姿を知ることができますね。
※学習計画表については別記事にてまとめましたので、下のリンクよりあわせてご覧ください。
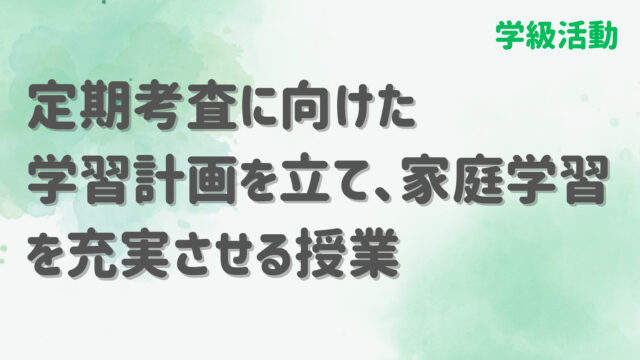
②家庭での様子
ここでは普段の生徒との会話や、学校独自で行っている(または委員会が主催している)学校生活アンケートなどで気になった点をまとめます。
私の場合は家庭学習や生活習慣についてよく話題にあげますが、最近では特に「スマートフォンの使用状況」について情報を集めることが多いです。
中学生になってからスマートフォンを持たせるご家庭も多いので、家庭での使用状況やそれに伴うルールづくりに関する情報は、保護者側から一定のニーズがあります。

スマホはルールを決めてから持たせることが超大事よね。
もし、アンケートに自分が集めたい情報に関する設問が無い場合や、特定の項目についてさらに深掘りして調査したい場合は、担任オリジナルのアンケートをつくって実施するのもひとつの手です。
ただ、残業必須の忙しい毎日の中でアンケートを作り、集計することは至難の業です。
そこで、今回は個別の保護者面談をテーマにお伝えしていますが、同様に学級懇談会の準備についてまとめた記事の中で、私オリジナルの生徒用アンケートを付録にしていましたので、よろしければそちらもご参照ください。

③これからの学習・生活
これからの学習・生活については、①「これまでの学習・生活」でまとめたことをもとに、今後の学校生活で生徒が何を意識していくと良いか、前向きで具体的な提案を検討します。
特に3年生は進路についての方向性を話し合う機会にもなるので、事前に生徒と面談して希望を聞いたり、それに対する進路情報をまとめたりすることが必要です。
また、生徒の課題について保護者の方に伝える場合(例えば授業中の態度など学校生活における各種改善点)は、思いつくものすべてを伝えようとするのではく
「特にここだけは、なんとかしたい」と思う大きなものを、1つか多くても2つまでにしぼって伝えた方がいいです。
実際に保護者の方へ伝える際は、
「〇〇さんには現在このような課題があり、こうするともっと〇〇さんの良さを活かせるはずなので、〇〇さんがそうしようと思えるような声掛けや、サポートの仕方を工夫していきたいと思っています。」
といったように、あくまで「担任として該当する生徒とどう向き合っていきたいか」という形で表現することを意識します。
先に述べたように、面談は保護者の方と良好な協力関係を築くことが目的なので
くれぐれも保護者に対して生徒の欠点をズバズバ指摘して、保護者が疲弊して帰っていくようなことだけは絶対に避けましょう。

改善点を聞く方は少なからずストレスがかかるから、最大限配慮して伝えることを忘れないようにしたいね。

普段の見取りや、生徒との関わりから得た情報は随時記録をとっておくと良さそうだね。
面談当日の流れ
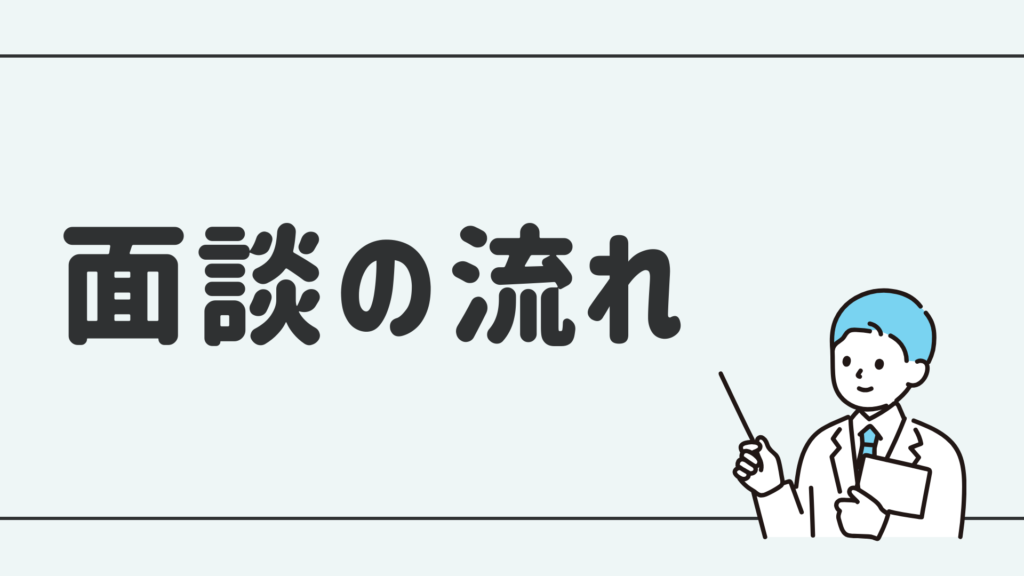
準備物は学校や学年ごとに異なると思いますが、参考例として私が普段面談時に教室へ持って行く物のリストを載せさせていただきます。
- 気になる情報を事前に記入した「進行+記録補助シート」
→今回の付録資料(このページ下部にご用意しています) - 考査結果一覧表
- 学習計画表
- 学校生活アンケートや各種振り返りシートなど
- 勉強法についてまとめられた市販の書籍
- 進路関係の資料(市販の県内高校ガイドブックなども)
- 生徒の作成物などで保護者に見せたいもの
- 自分用のPC、筆記用具、水筒

付録の【進行+記録補助シート】はページ下部にご用意しています。
ステップ1:これまでの学習・生活
忙しい中わざわざ時間をつくってくださったことに感謝の気持ちを伝え、ちょっとした雑談の後面談を始めます。
私の場合、まず最初に「ご家庭で学校の話をされますか?」と聞きます。
もし頻繁に学校の話をしているようであればどんな話をしているのか教えていただき、それに付随するエピソードなどを伝えるようにします。
反対に家庭で全く学校の話をしていない場合は、「もし気になることなどございましたら、遠慮なくおたずねくださいね」と伝えます。
その後は進行+記録補助シート(付録のPDF資料)に記入したことをもとに、これまでの学習面と生活面について肯定的に伝えます。
特に友人関係について心配されている保護者の方は少なからずいらっしゃるので、休み時間の過ごし方などを伝えるのも良いと思います。

先はまだ長いので伝えることは簡潔に。教員側の話が長くならないように注意です!
ステップ2:家庭での様子
学習面と生活面について伝えたら、「学校では〇〇な様子が見られました(良いこと)が、ご家庭ではどうですか?」という質問から発言機会を保護者の方に移します。
そして会話の流れの中で、事前に進行+記録補助シート(付録のPDF資料)に記入していた気になった点についての質問をはさんでいきます。
先にも述べましたが、私の場合は家庭学習や生活習慣、スマートフォンの使用などについて話題にあげることが多いです。

ここでは会話の内容ができる限りポジティブになるよう意識します。
ステップ3:困っていることや担任と共有しておきたいこと
家庭での様子を聞き取る中で保護者の困り感が見えた場合、それについて深堀りしていきます。
ここでは、「家庭での困り感を共有して一緒に考えようとする姿勢を示す」ためにカウンセリングマインド(受容・傾聴・共感)で保護者のお話をしっかり聞くことを最優先にします。

【 伝える < 聞く 】ってことね。
また、生徒の課題について保護者の方に伝えることがある場合(例えば授業中の態度など、学校生活における各種改善点)は、この会話の中で
「実は学校でもこうしたことがありまして…」
と保護者の発言につなげるかたちで伝えると、スムーズに話題にあげることができます。
その際、先にも述べたように担任から生徒の課題について伝えるときは、こちら側の見解を一方的に伝えて終わることは避け
「担任として生徒とどう向き合っていきたいか」という形で表現したり、
- 「〇〇さんは△△について苦手意識がある様に見られたのですが、ご家庭ではいかがですか?」
- 「もし、ご家庭で意識されていることなどございましたらアドバイスいただけますでしょうか?」
といったやわらかい表現で伝えるようにし、あくまでも「お子さんについて一緒に考えたい」という姿勢を示します。

基本はこれまでの生徒の頑張りを認め、それを保護者に伝えることを優先します。
生徒の課題を伝える際はその伝え方に十分配慮しましょう!
ステップ4:これからの学習・生活
最後に、ここまで保護者の方から聞き取ったことや進行+記録補助シート(付録のPDF資料)に記入したことをもとに、これからの学校生活で生徒を育てていく方向性について相談します。
私はよく
「これからの学校生活で、お子さんにつけてほしい力や、担任からの関わり方などで希望されることはございますか?」
とたずねます。
その際聞き取ったことは必ず記録し、それを意識した生徒との関わりを継続する中で、新たに得られた情報や課題、そして生徒の成長をまた次の面談で保護者と共有していきます。
もちろんここでも、面談の優先事項である「家庭での困り感を共有して一緒に考えようとする姿勢を示す」ことを徹底し、終始感謝の気持ちを持って丁寧な対応を心がけることが必要です。
ここまで述べてきたように、私の場合は
- 学校の様子を伝える
- 家庭での様子を教えてもらう
- 生徒の課題について共有する
- これからの方向性について一緒に考える
という4つのステップで面談の基本的な流れを構成しています。
特に最後は明るく、前向きにこれからの話ができるよう意識しましょう。

終わり方って強く印象に残るから大事よね。
気をつけたい3つのポイント
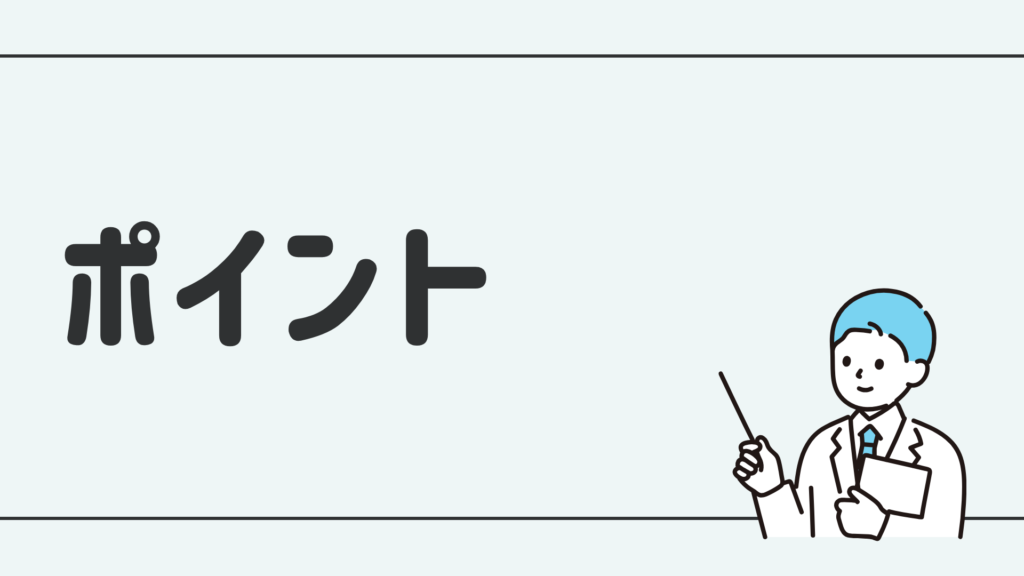
保護者面談をする際、これまでまとめてきたことと併せてぜひ意識してほしい3つのポイントについてお伝えします。
どれも細かいことですが、特に3つ目は不要なトラブルを避けるためにもかなり重要です。
- 時間を守る
- 面談の順番を工夫する
- 迷ったら即答を避ける
①時間を守る
これは文字通り開始時間と終了時間は厳守するという意味です。
保護者の方は忙しい時間の合間を縫って来校しているので、ひとつ前の面談が長引いて次の保護者を待たせてしまったということは絶対に避けたいです。
そのためには、②「面談の順番を工夫する」にも通じますが、全体を通して時間に余裕を持たせたプランニングが必要になります。
面談中であれば、あれもこれも全部伝えようとするのではなく、伝えることを事前にリストアップして優先順位を付け、保護者の発言量と残り時間を考慮しながら会話の流れを柔軟に組み立てていけるとgoodです!

手札のカードは10枚用意するけど、実際はその内の5~6枚を使って面談を進め、終盤は状況を見つつ使うカードの枚数を加減していくイメージです。
一方でしっかり準備したにも関わらず、思っていた以上に時間が余ってしまう場合もあるわけですが
だからといって、単なる帳尻合わせの会話をぐだぐだ続けるのは避けた方がいいというのが今の私の持論です。
私は初任の頃、保護者の方から特に質問なども無く、時間が余ってしまった場合「何とか間を持たせなければ!」と思い、設定時間いっぱいまでダラダラと一方的に話を続けていました。
しかし考えてみると、この後に仕事や他の予定が入っている方もいらっしゃいますし、何より「聞きたいことや話したいことがあれば言われるはずだよなぁ」と思うようになり、それ以降無理に会話を引っ張ることはしないようになりました。
基本的に設定時間の残り5分程度で「その他、何か気になっていることやお話したいことなどはございませんか?」と質問し、特になければ挨拶をして終わるようにしています。
②面談の順番を工夫する
滞りなく面談の日程を進めていく上で、その順番決めは重要です。
こちらから伝えることが多くある家庭や、普段の電話対応などで時間が長くかかりがちな保護者については
面談時間をその日の最後に設定して、じっくりお話しできる時間を確保するのか、
あるいはその反対に、あえて他の保護者と連続させて設定するのかを検討します。
(他の保護者と連続させて設定すると、「次の面談がございますので…」と会話を切り上げやすくなります)
また、同じ学校に兄弟姉妹がいる生徒の保護者面談は、その兄弟姉妹が在籍する学級担任の先生と事前に日程の調整をしなければなりません。

私の場合は、面談が3回ぐらい続いたら間に空き時間を1回挟むようにして日程を組んでいます。

それなら急遽保護者が遅れてくる場合も対応できそうだね。

それまでに行った面談の記録をまとめたり、次の面談の準備もできたりするから、気持ちに余裕を持てるようになるね。
③迷ったら即答を避ける
これはいわゆるリスクマネジメントにあたります。
不要なトラブルを避けるためにも、自分1人で判断することに不安がある場合は
「確認の上、改めてご連絡させていただきます」
と保護者の方に伝え、面談後学年主任に確認するようにします。

「大丈夫です!」って言った後の「やっぱりダメでした」は避けたいよね。

確認したあとの報告もセットで忘れずに。
まとめ
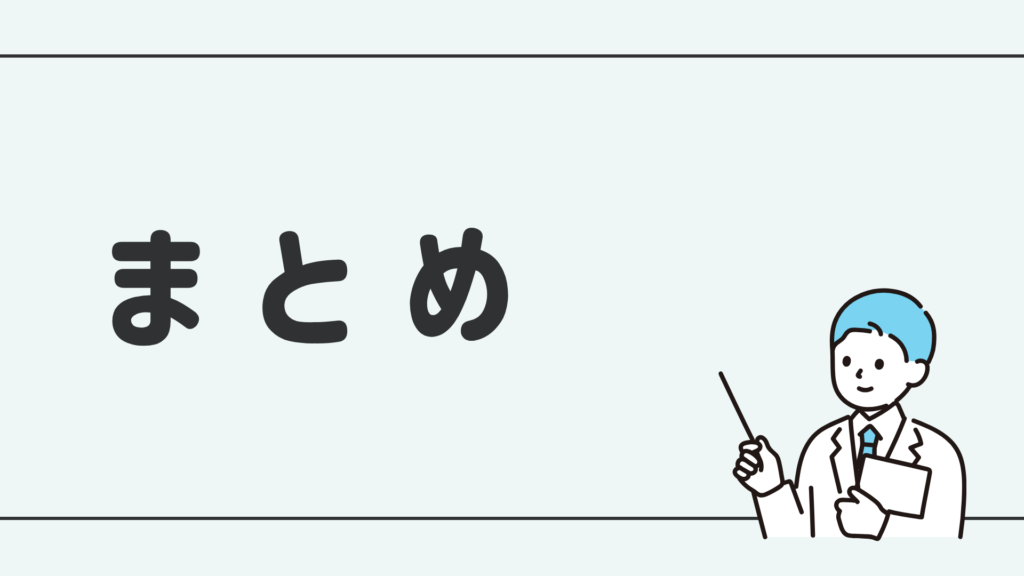
ここまで、おすすめしたい保護者面談の事前準備と当日の流れについてご紹介させていただきました。
先に述べたように、私は『この面談を通して、保護者の方と良好な協力関係を築く』ことを目的として設定し、常にその達成に向けた関わり方を意識しています。
それは、学校だけで生徒指導を行うよりも、家庭と協力して行うことでその効果を格段に高めることができると考えているからです。(担任の精神的な余裕にも大きく関わります)
もちろん簡単に達成できることではありませんが、担任のそうした姿勢を保護者の方に少しでも理解していただけるよう、できる限りの準備をして面談の日を迎えたいですね。

先生方の普段のがんばりが、しっかり保護者に伝わるよう祈っています!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
日々走り続ける全国の先生方へ、敬意を込めて。
※今回の付録シートは下の【PDF資料】ボタンからダウンロードしてください。
↑クリック