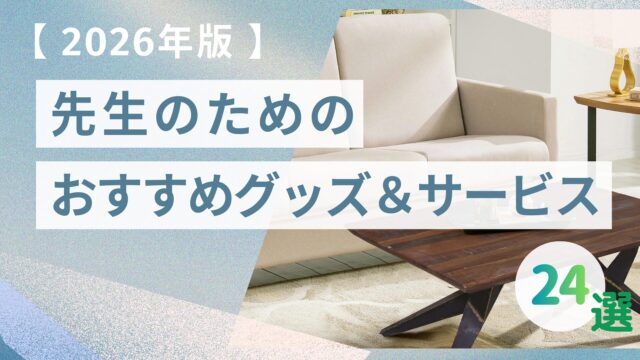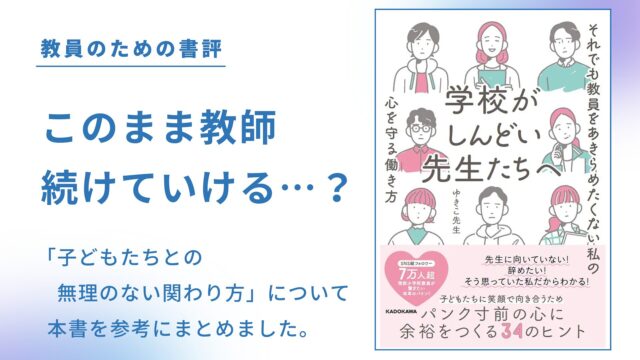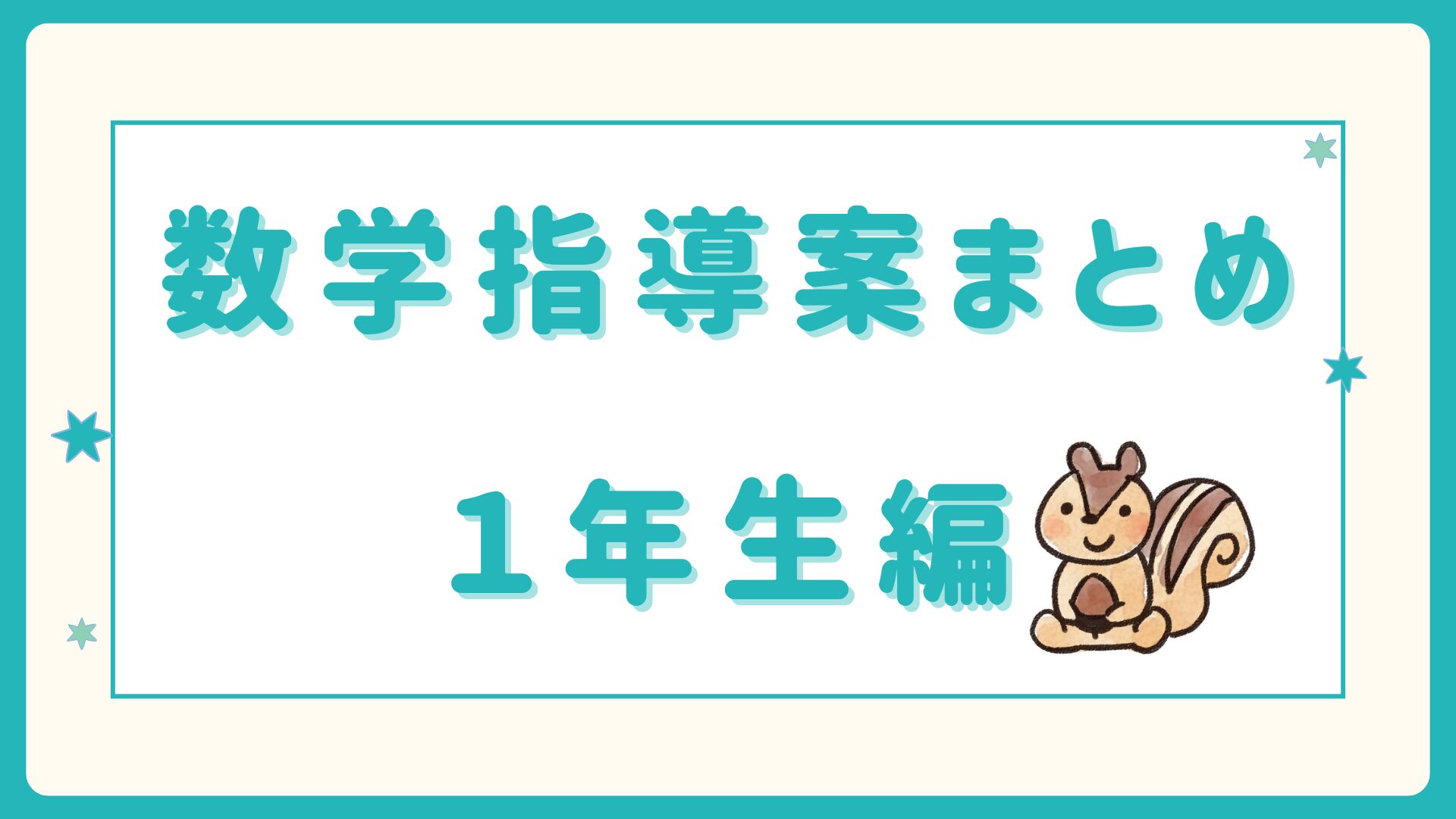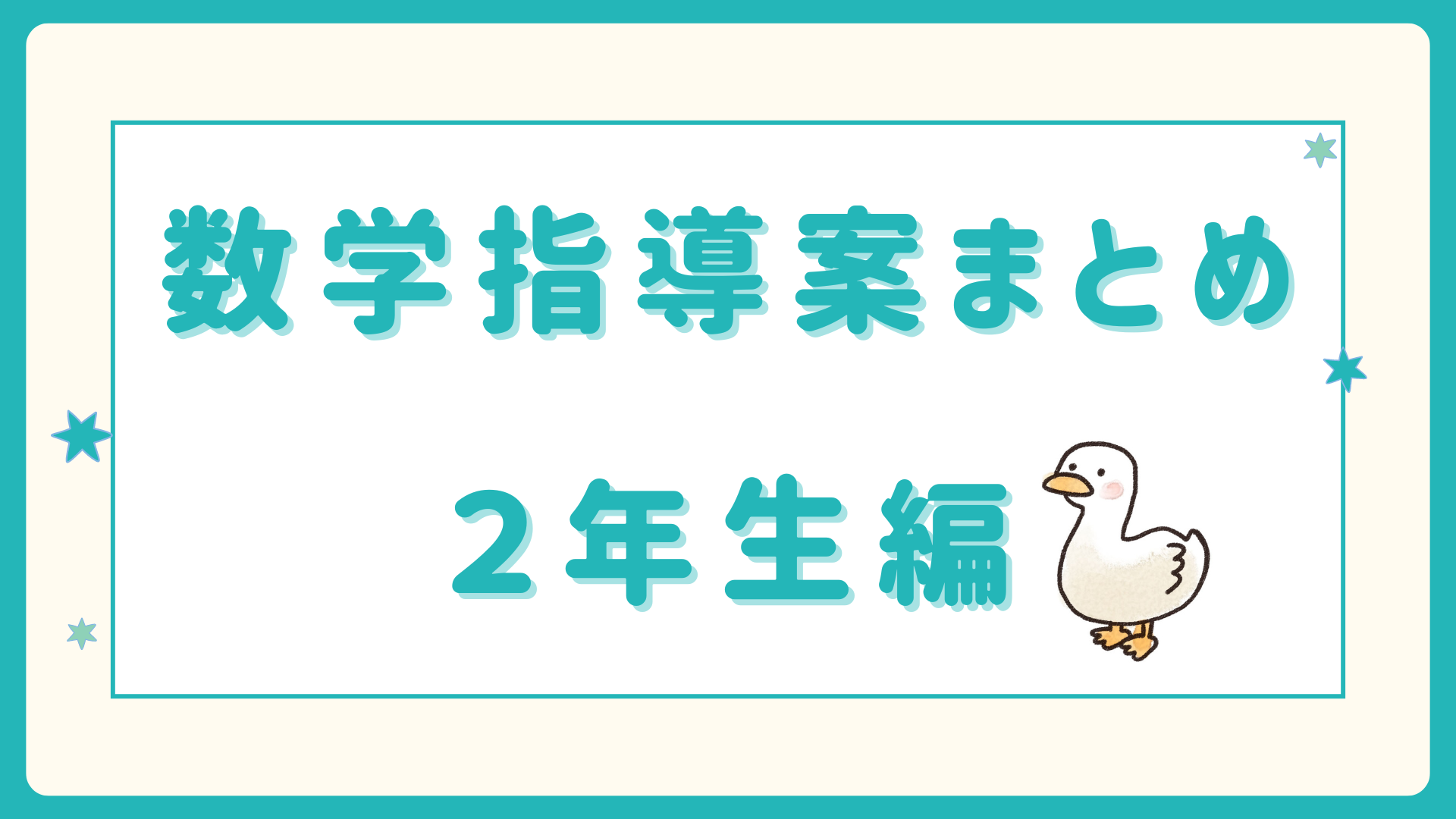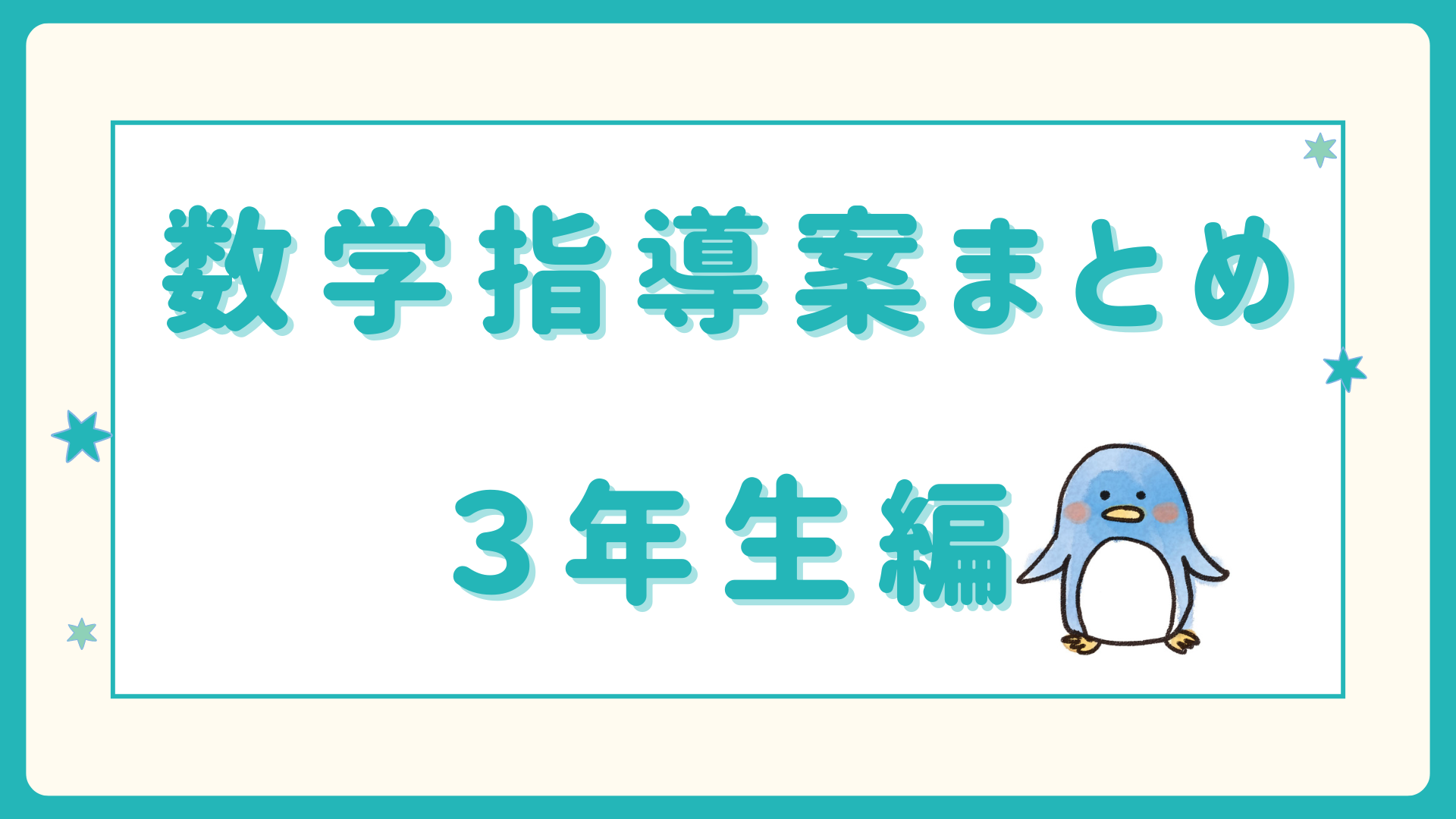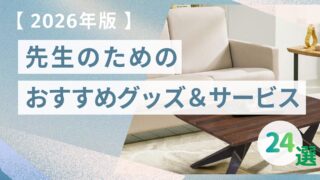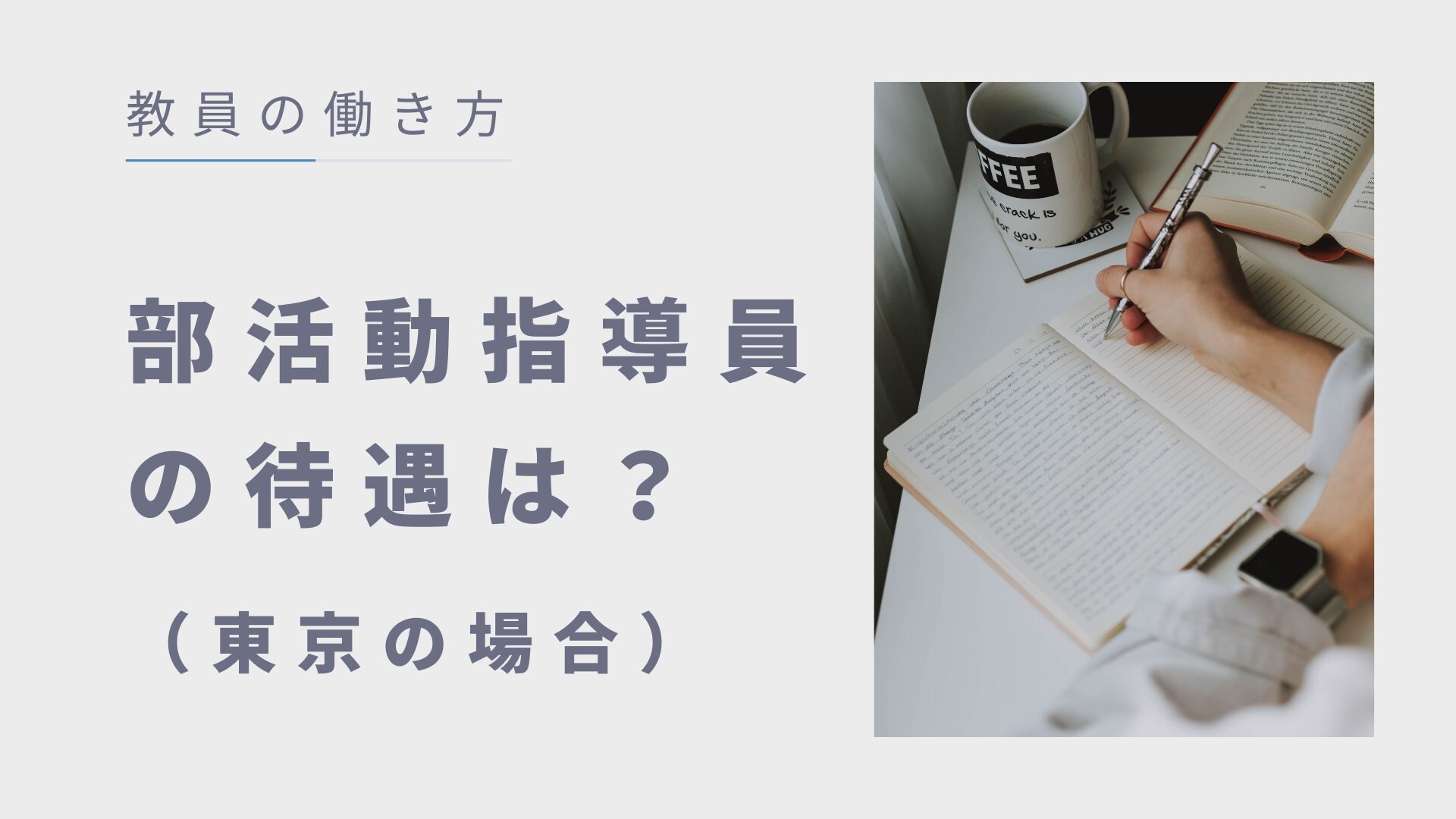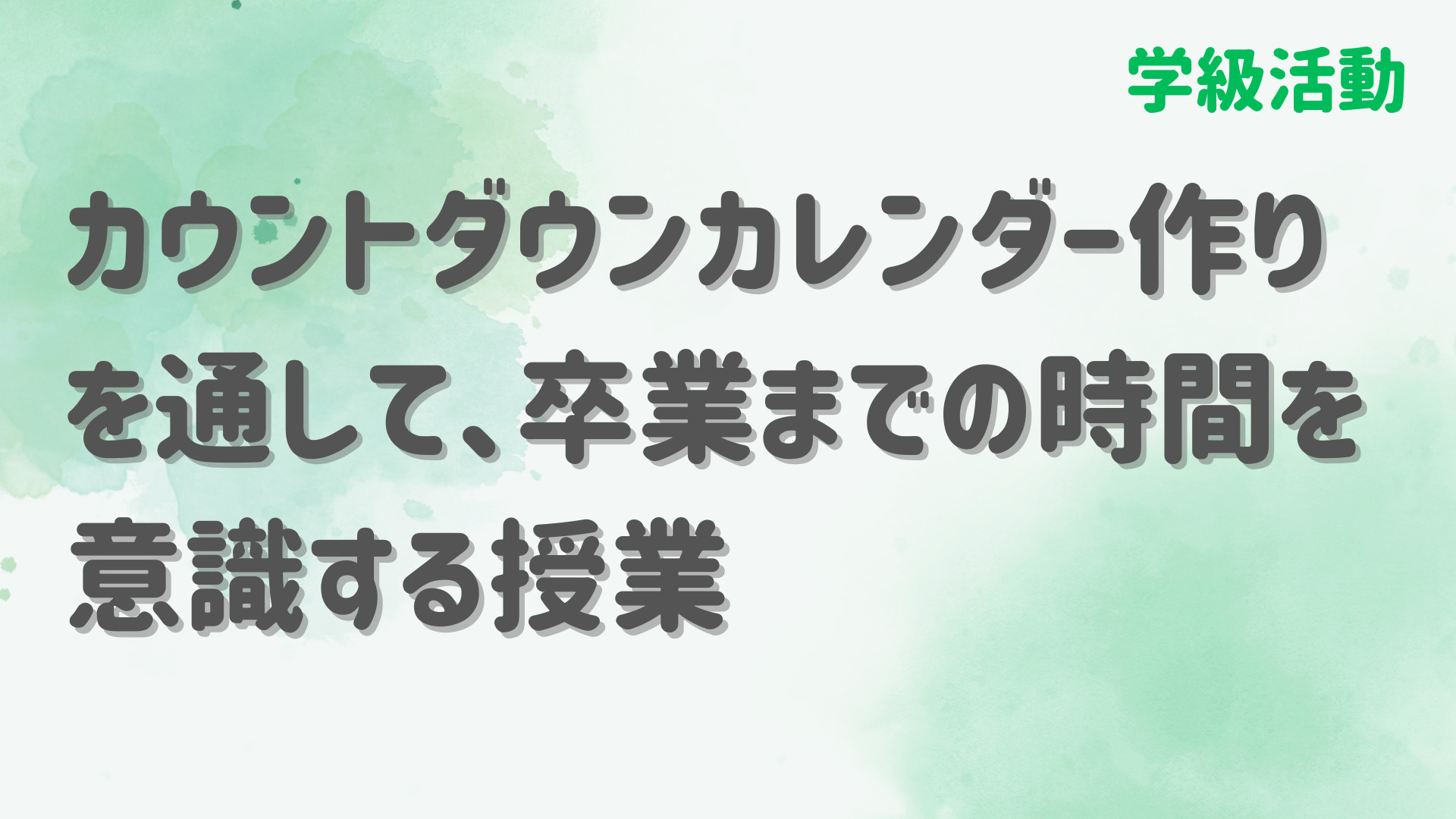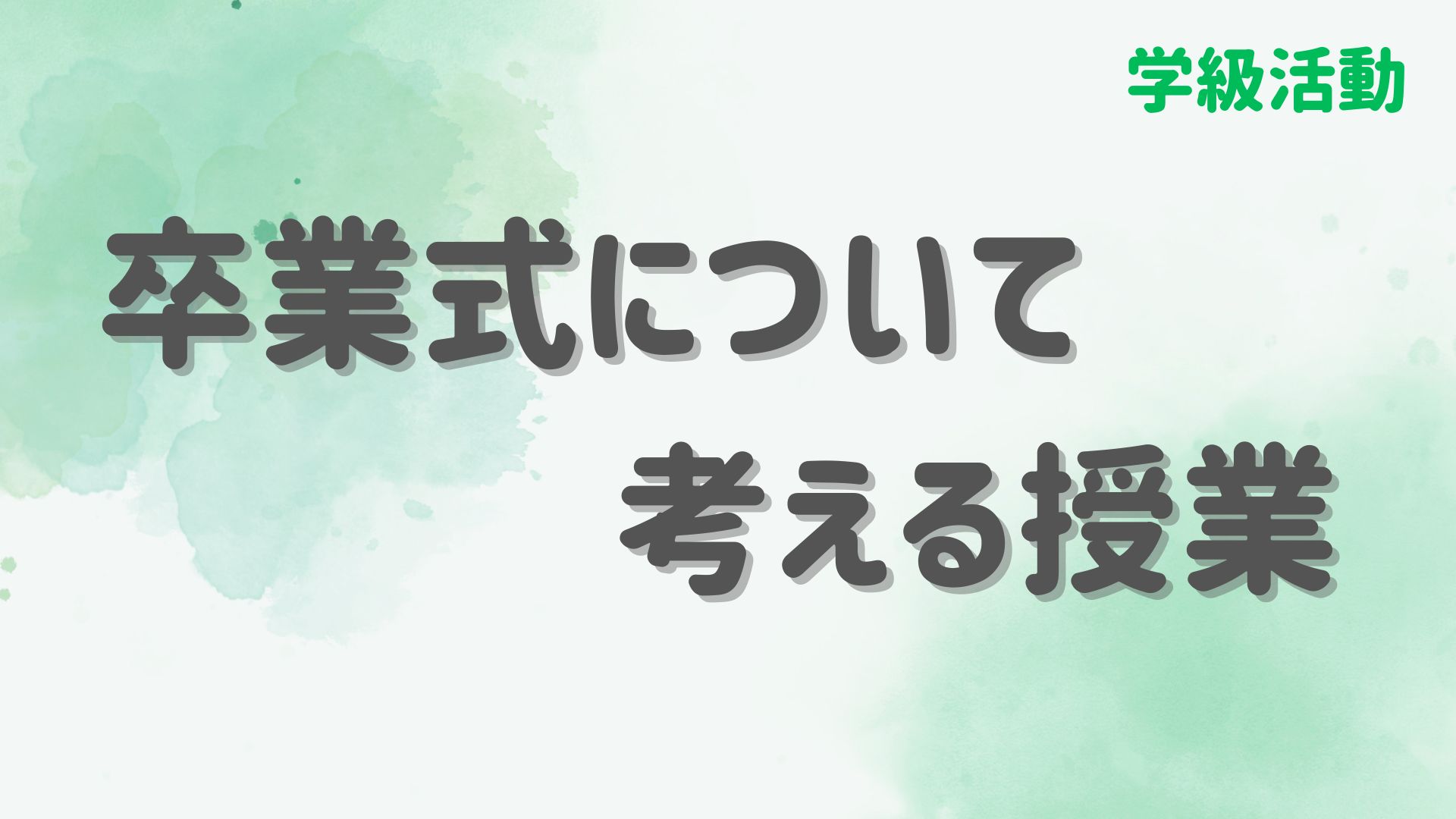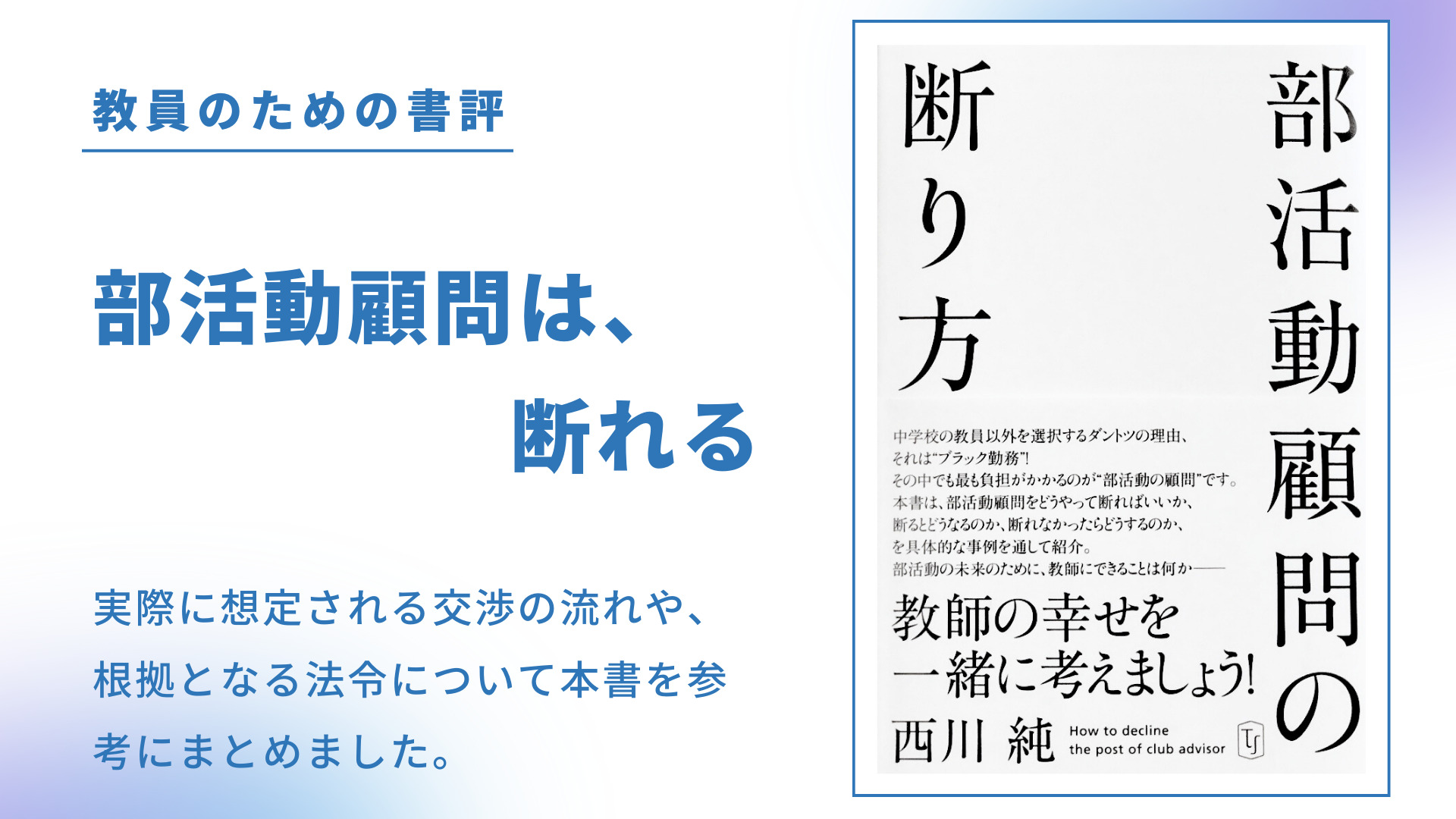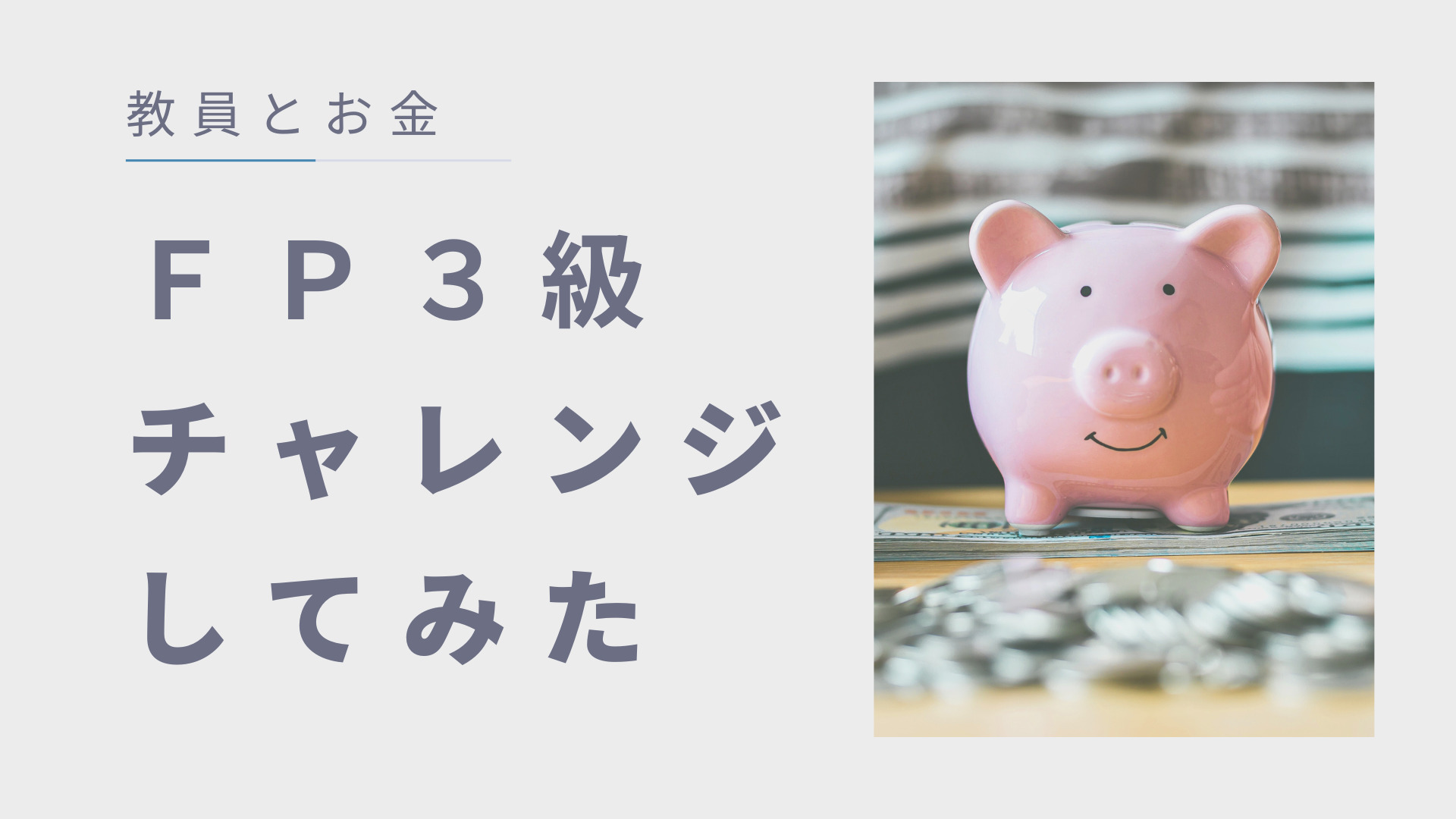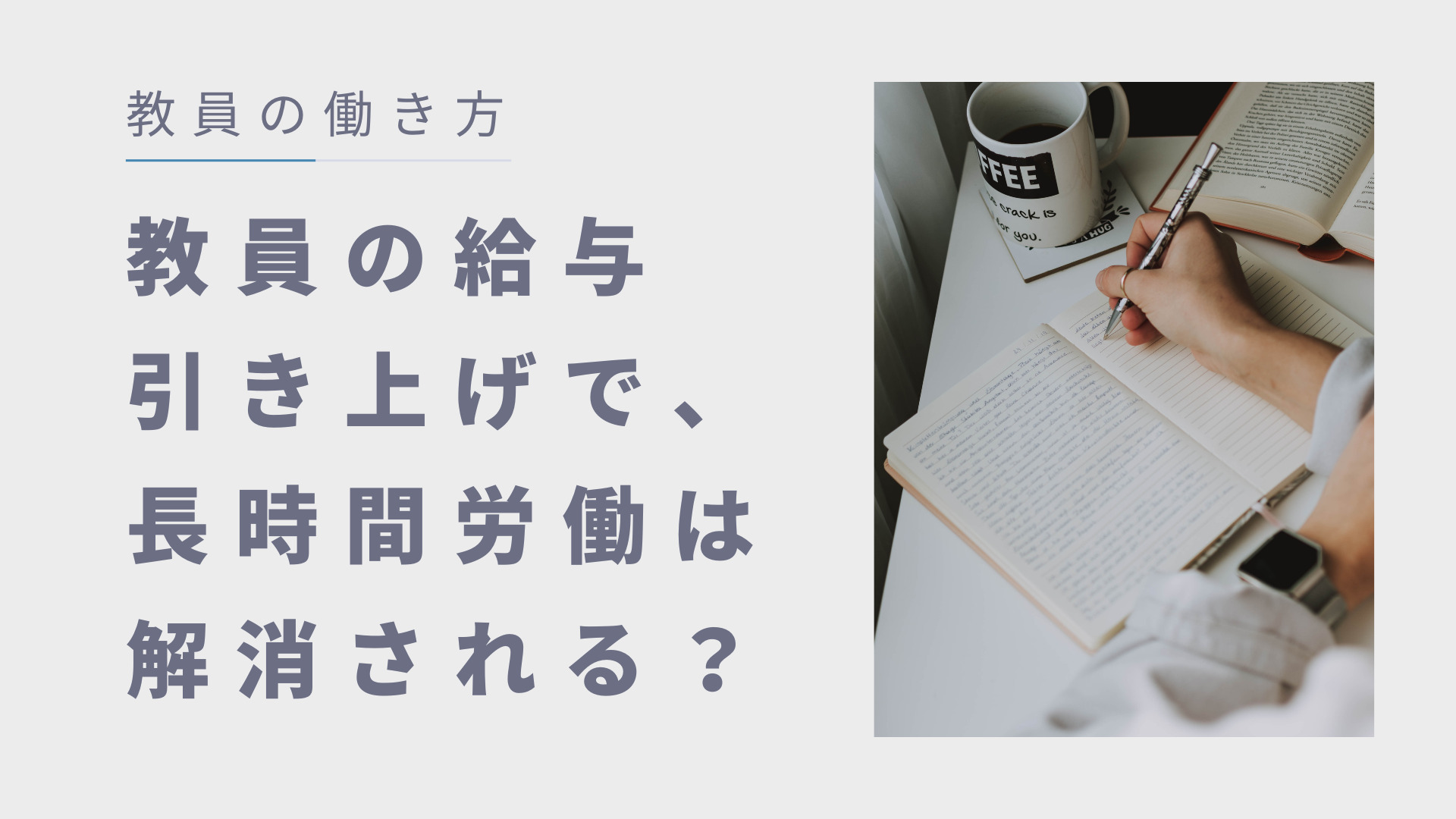生徒の主体性を育む中学数学の授業づくりについて【ポイントまとめシート付き】

今回は、私が普段数学の授業づくりをする上で大切にしていることをまとめてみました。
このブログでは、私がこれまで実際に行ってきた数学の授業について、その具体的な流れと、それをスムーズに実現させるためのワークシートを
誰でも簡単に、すぐ実践できるよう調整して発信していますが、
この記事を読んでその背景にある意図を汲んでいただけると、作成者としてこれほど嬉しいことはありません。
見当違いなことを言っているところがあるかもしれませんが、そこはひとつの考え方として受け取っていただければ幸いです。

「今日は疲れて自炊するのしんどいから、スーパーでごはん買っていこうかな」みたいな感覚で気軽に使える、【授業のおそうざい屋さん】を目指してます!
※ご紹介しますのは個人の実践に基づく見解ですので、予めご了承ください。少しでも先生方のご参考になれば幸いです。
今回ご紹介する「数学の授業づくりのポイント」についてまとめたPDF資料を、ページ下部にご用意しました。
ぜひダウンロードしてご活用ください。
【 各学年の授業案リンク 】
何のために学校で学ぶのか
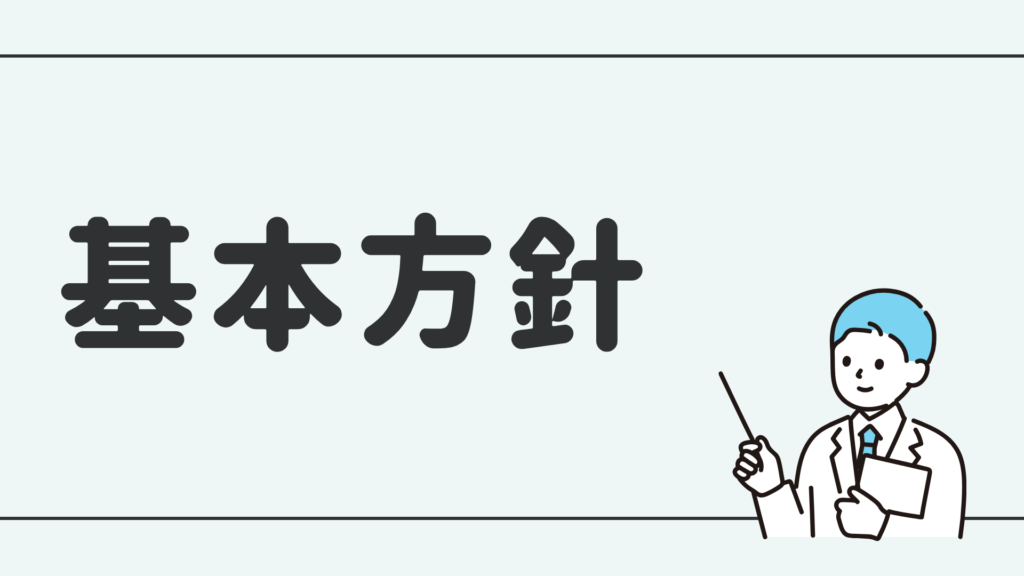
私が数学の授業づくりで大切にしているテーマは
削れるところを徹底的に削ることで、生徒が問題と向き合う時間や生徒同士の交流の時間を最大限確保し、数学の授業を通して生徒の主体性と協働力を育てる 。
です。
これは私の授業づくりにおいてその土台となる最も根本的な考え方であり、その先に知識・技能の習得や数学的思考力・判断力・表現力の育成があると考えています。
教員としてはちょっと言いにくいことですが…
正直、「数学のテストで高得点を取る」ことに限っていえば
本人にやる気さえあれば、家でYouTubeを見ながらでも十分に達成できると思うのです。
だからこそ、わざわざ学校に来て集団で勉強する意義は何なのかを考えたとき、その最たるものは
「生徒同士の直接的な関わり合いの中で、社会性を身に付けること」
なのかなぁと個人的に感じていました。
教科における学び と 人としての成長
この2つを同時に経験できることが、日々学校で行われている授業というものの本来の価値ではないかという捉えです。
とすれば、YouTubeやその他の媒体で代替できるような「授業者からの一方的な知識の伝達」は最低限にとどめた上で
生徒同士が交流するきっかけをうまく作り、共に学んでいこうとする雰囲気を醸成させることが授業者の大きな役割になるのではないでしょうか。

まさに、授業を通してクラスづくりをするということです。
そうした意味で私は授業づくりの際、「どうすれば生徒たちがわかりやすいだろう?」と考えるより、生徒同士の交流を誘発させるため
「どうすれば生徒たちが困るだろう?」
と考えることを優先しています。(私はこの考え方を“意図的不親切“と勝手に名付けています)

教えない授業って、そういうことね。
削れるところを徹底的に削る
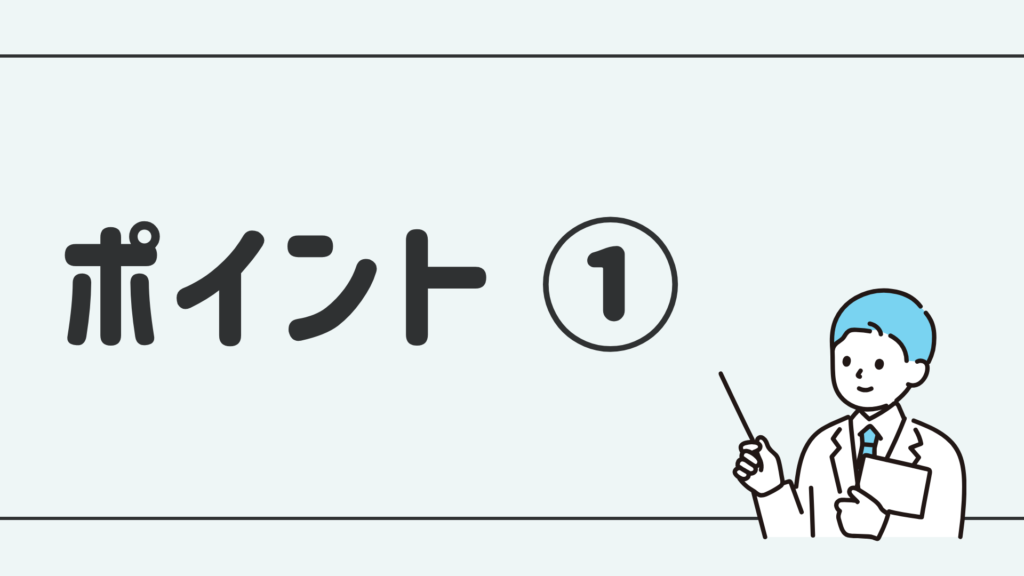
板書を必要最低限にする
できるだけ板書はしない方向で考えますが、どうしても必要な場合は最低限の情報量でまとめることを意識します。
これは授業者が板書にかける時間と、生徒が板書をノートに書き写す時間をできるだけ減らすためです。
また、あえて情報量の限られた板書にし、口頭による解説の比重を大きくする(意図的不親切)ことで、その後生徒が解説を思い出しながら頭の中で整理し、自分の言葉としてノートにまとめることをねらいます。(よってノートのまとめ方は個人ごと異なります)
もちろん、こうしたやり方は生徒にとって容易なことではないので、ノートづくりをする際は教科書を確認したり、他の生徒のまとめ方を参考にしたりすることも勧めます。
こうすることでノートづくりが単純な板書の書き写し作業で終わることを防げますし、生徒同士の交流機会を増やすことにも繋げることができます。

授業者は個々のノートづくりの工夫や、他者と協力して学習しようとするクラスの雰囲気を肯定的に評価していきます。
そして、これらを実現させるためには
授業者が解説している時は聞くことだけに集中させ、その後にまとまったノートづくりの時間を確保する
ことがポイントとなります。

「聞く」と「書く」を少しずつ交互に繰り返すのではなく、それぞれ1回ずつまとまった時間を確保するイメージね。
また、板書は生徒が問題を解いている間に9割完成させることを基本とし、授業者が解説しながら板書をして、生徒がそれを待つという時間を無くすことも重要です。(9割に留める理由は後述します)
全体に向けた問題の解説を必要最低限にする
授業者が全体に向けて問題の解説をすると、すでに理解できている生徒もそれを聞くことになるため、効率はあまり良くないと思っています。
またこれは個人の見解ですが、授業者が丁寧に解説すればするほど生徒の主体性や交流活動に対する意欲も低下してしまうように感じます。

授業に対して”受け身”になっちゃうってことね。
よって、全体に向けた解説は特に注意が必要な問題のみに限定して行い、その他の問題はあえて答えのみ提示する(意図的不親切)ようにしています。
そうなると不正解だった問題は教科書を参考に自己解決するか、授業者へ個別に質問したり、他の生徒に教えてもらったりしなければなりません。
この時に生徒の立ち歩きを認めたり、学習班での交流機会を設定すると
教室内のいたるところで生徒(ミニティーチャー)による生徒のための個別指導が始まり、時には授業者顔負けの立派な説明をする生徒が現れることもあります。
このように、個別のつまずきは基本的に生徒同士で解決させることを意識しています。

つい、「あれもこれも教えてあげなくては!」と考えてしまいますよね。
ただし、次の授業時には前時の学習内容を忘れている生徒がいるなど、全体の理解度が下がっている場合がほとんどなので
最初は前時の復習問題を解くことから始め、授業者の解説によって前時の学習を補完するようにします。(生徒が復習問題を解いている間に本時の板書を9割完成させます)

1回の授業で100%を目指すんじゃなくて、「本時の授業」+「次時に行う復習問題」で完成させていく感じね。
一方で、こうした授業スタイルをとると「何もしない生徒」が現れることもあります。
しかし、その生徒自身の意思に基づいて「何もしない」という選択をとっているのであれば、他人に迷惑をかけている場合を除いて、私はそれに対して指導したり何か活動を強制したりはしません。
あくまで授業者にできることは“魅力的な授業の提供”と“必要に応じた個別のサポート”であり、その先のことは生徒自身が決めることだと考えているからです。
時間と周りの環境が解決してくれることは大いにあると思いますので、意欲の低い生徒は見捨てるということではなく、「あなたが求めるならいつでもサポートするよ」というメッセージを送り続けながらチャンスを待つというスタンスをとっています。
もちろん、意欲はあるけれど他者とコミュニケーションをとることが苦手で、個人の力ではうまく学習を進められないという生徒の場合は、適宜授業者がサポートします。
挙手を求めない
挙手を求め生徒個人の考えを全体で共有することについて、その学習効果を否定するつもりは一切ありません。
しかし私の個人的な見解として、生徒に挙手を求めることには
- 挙手をする生徒の固定化
→その他の生徒は人任せになりやすい - 挙手が無い場合の対応
→授業のテンポが崩れネガティブな雰囲気になりやすい - 問いに対する答えがズレている場合の対応
→個人のフォローで全体の流れが止まってしまう
以上のようなデメリットもあると考えています。
よって「削れるところを徹底的に削る」という観点から、私は生徒個人に何かを発表させるということはあまりしません。
一方で、解説中は「ここを計算すると答えは何になる?」「この法則って何だっけ?」など、1問1答形式の簡単な質問を全体に向けてかなり頻繁に行います。
これは質問の答えを考えながら授業者の解説を聞くことで、生徒が完全に受け身の状態になることを避けるというねらいがあります。
またこのような場面での質問はテンポを最優先にして、
答えてくれる生徒がいれば「その通り!」「おしい!」とだけリアクションし、無反応の場合は「○○だよね」とすぐに切り上げて
テンポを崩さないよう気をつけながら解説を続けていきます。

生徒の無反応を流してしまったら、質問する意味がないのでは?

ここでの質問の目的は「生徒の理解度を確認する」ではなく、「生徒が受け身になることを避ける」です。
私たちも研修会で講師の先生が全体に向けて質問した時、リアクションすることに一瞬ためらってしまうことってあるよね。

たしかに、大勢の前で挙手をしたり発言したりするのはちょっと勇気が必要だね。

その時って質問する側からすると無反応のように見えるけど、質問される側はその質問に対する答えを自分なりに考えているはずなんだ。

ふむふむ。

私はそれだけで十分価値があると思う。
もちろん、生徒がいつでも安心して自分の考えを言えるように、クラスの雰囲気づくりは時間をかけて継続していくよ。
以上のように、基本的に私は生徒個人に何かを発表させることはあまりしないのですが、学習内容によっては生徒個人の考えを全体で共有した方が良い場面もあります。
そうした場合は、あらかじめ机間巡視中に発表させる生徒を決め、その生徒に予告してから指名して発表させるようにしています。(意図的指名)
こうすることにより、授業者側が予想していなかった生徒の発表にアタフタしたり、それを訂正したりする必要が無くなります。
また、指名された生徒は自分の考えが間違っていないということが分かるので、自信を持って発表することができますし、発表者の固定化を防ぐこともできます。
同時に、教員の授業に対する考え方や、生徒に期待することなどを普段から積極的に生徒へ伝えていくことも重要であると考えています。
授業の効率化を図るという意味では、1時間ごとにワークシートを準備してそれを基に授業することもかなり有効だと思います。
一度作ったワークシートは同じ学年を担当する際に繰り返し使えますし、授業後に改良を加えていくことで年々授業の質を高めることもできます。
また、ワークシートをTV画面に表示することで授業者が板書にかける時間を削減できるほか、ワークシートの作り方次第で生徒が書くことにかける時間もコントロールすることができます。
生徒の主体性と協働力を育てる
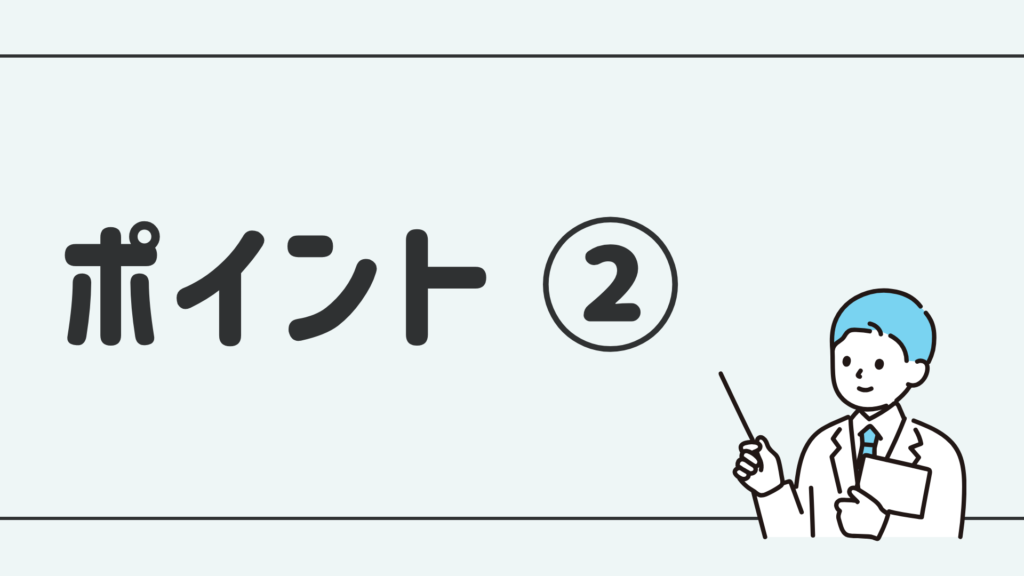
めあて(ゴール)を設定する
生徒がその時間で何をできるようになれば良いのか、あらかじめ具体的に示すことを心がけています。
また授業の最後にはそのめあてを達成できたかどうか、生徒自身で振り返る機会も設定しています。
私はよく勉強を筋トレに例えるのですが、ゴールの見えない筋トレはただの地獄であり、簡単にモチベーションも下がってしまいます。
「今日はどこを重点的に、どんな方法で、どのくらいの量でトレーニングし、どうなることを目指すのか」
これを理解してトレーニングすることで、モチベーションの低下を防ぎ、効率良く効果を上げることができるようになるはずです。
生徒主体の活動時間はまとめて設定する
「挙手を求めない」でも少し触れましたが、私は授業の流れをなるべく切らないようにすることを意識しています。
特に、”授業者の解説”と”生徒主体の活動”を交互に行うことは避け
一度生徒主体の活動が始まったら、その時間をできるだけ長くまとまった状態で確保するようにします。

「聞く」と「書く」を少しずつ交互に繰り返すのではなく、それぞれ1回ずつまとまった時間を確保するってやつね。
こうすることで生徒に時間的な余裕が生まれ、じっくりと問題に向き合うことができるようになるほか、他の生徒と交流することに対する意欲の高まりも期待できます。

前半は復習とめあての確認後、今日の学習内容の重要ポイントを最短でおさえて、後半はずっと生徒主体の活動をするみたいなイメージです。
できるだけ生徒の活動を制限しない
生徒の中には、他の生徒と交流することに抵抗がある生徒もいます。(その割合は年々増えている気がしますね)
そうした場合、授業者としてはできれば交流を勧めたいものですが、それがきっかけで数学の授業が苦痛になってしまっては本末転倒なので
どうしても必要な場面を除き、基本的には生徒に交流活動を強要しないようにしています。(個人でじっくり問題と向き合うのもアリということです)

たしかに交流を強制されるとつらい場合もあるよね。

私はよく「個人でじっくり考えてもいいし、周りに相談してもいいよー!」と声をかけるようにしています。
また、問題集の使い方やノートのまとめ方についても、生徒それぞれに合った学習方法があると思っているので、基本的に生徒のやり方を尊重しています。
特に問題集については、一律に全ての問題を解かせるのではなく、生徒が自分のレベルに合った問題を選んで解くことを認めています。
ただし学習がうまく進んでいない生徒に関しては、授業の受け方や問題集の使い方、ノートのまとめ方などを適宜授業者が個別にアドバイスしていきます。
プロセスを肯定的に評価する
授業の最後、生徒はめあてに対する自身の学びを振り返って自己評価しますが、私は学習に向かうクラス全体の様子を評価します。
自ら学ぼうとする生徒の姿勢や、他者と協力して学ぶクラスの雰囲気を肯定的にフィードバックするのです。
こうすることで、生徒同士の交流の活性化を図り
「ひとりで勉強するより、みんなで勉強した方が楽しい!」
と感じてもらえるようにしたいです。
また、クラスへの所属感や、全体の連帯感を高め、授業を通してクラスづくりをすることもねらいの1つとしています。

自分がつくった授業で生徒同士が活発に交流している姿を見ると、やっぱり嬉しくなりますよね。
授業の質は、その9割が準備で決まると思っています。
「授業前に万全の準備を整え、授業中は生徒が主体となって活動しているのをただ見守る」
その結果、生徒は自分たちの力で成長することができたと感じる。
これが私の考える理想の授業です。
この考え方は授業だけでなく、生徒会活動や学校行事などその他の様々な教育活動にも通じるものだと考えています。
授業における約束
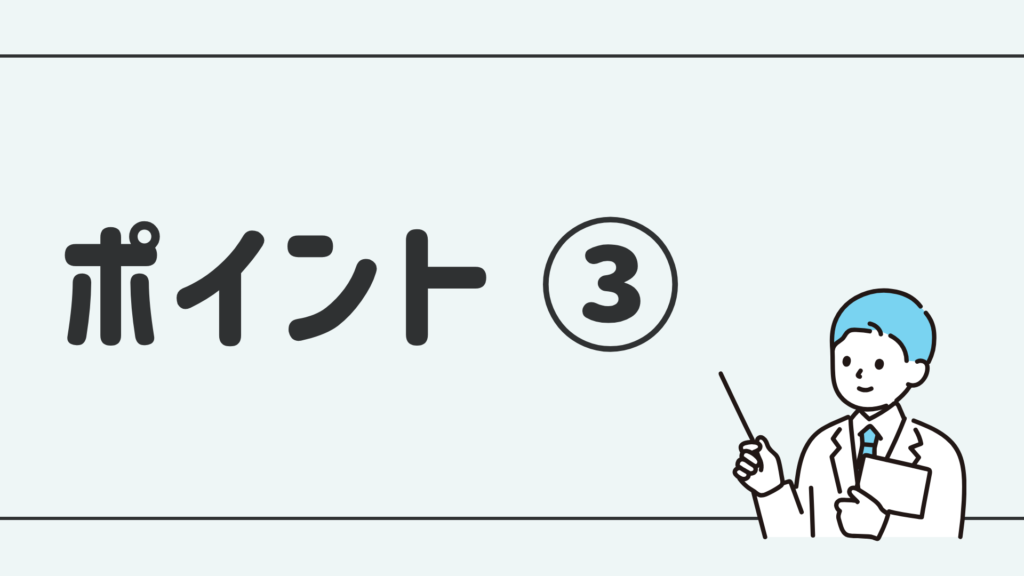
授業者が守る約束
- 可能な限り、授業終了のチャイムが鳴る5分前には授業を終わらせることを目指し、チャイムが鳴ってからも話し続けることは絶対にしない。
- 時間が余っても予定していた範囲以上に授業を進めない。
- 授業内で完結させることを目指し、基本的に宿題は出さない。
①については、主に振り返りの時間を確保するためですが、授業の最後に雑談をしたり、すこしリラックスして和やかに終わらせるためでもあります。
数学の授業が5分早く終わることは、生徒にとって大変魅力的なようで
「そのためにも、みんな私に協力してくれ!!」と言うと、授業者側と生徒側の利害が一致するので、比較的協力してもらいやすく、授業中に注意することも減りました。笑
②については、逆に活動が終わっていない(全ての問題を解き終わっていない)生徒がいても、活動時間は延長しません。
その理由は、生徒の主体性を育てることにも関連していますが
決められた時間内で目標を達成するためにはどうすればよいのか、生徒が自ら考えて行動することが重要であると考えているからです。(意図的不親切)
③については、ノートや問題集の回収、点検も行わないようにしています。
ノートは先に述べたように生徒それぞれのやり方を尊重していますし、問題集についても提出するために答えを丸写ししては意味がありません 。
ましてやそれをもって評価をつけることは、正しい評価からかけ離れた行為であるとも考えています。
②と同様に目標を達成するためにはどうすればよいのか、生徒が自ら考えて行動することを重視したいです。
生徒が守る約束
- 授業者が全体に向けて話をしているときは、手を止めて顔を上げ、聞くことに専念する。
- 困ったら助けを求め、助けを求められたらできる範囲で協力する。助けてもらったら感謝の言葉を伝える。
①については、「聞く」と「書く」を完全に分けることを徹底させます。その理由は、
- 普段から教員の指示を静かに聞ける雰囲気をつくる
- 聞きながら書くことにより起こる集中力の分散を防ぐ
の2つが挙げられます。
また「板書を必要最低限にする」でも触れましたが、授業者の解説を思い出しながら頭の中で整理し、自分の言葉としてノートにまとめることで
ノートづくりが単純な板書の書き写し作業で終わることを防げますし、生徒同士の交流機会を増やすことにも繋げることができます。
②については、学びに向かうクラスの雰囲気として、積極的かつ肯定的に評価していきたいです。(個人的には問題の正答率よりも圧倒的に優先順位が高いです)

私は生徒同士の交流を活性化させるために、あえて困っている生徒がいてもすぐには声を掛けません。
質問された時も「○○さんに聞いてみたら?」と交流を促すことが多いです。(意図的不親切)
まとめ
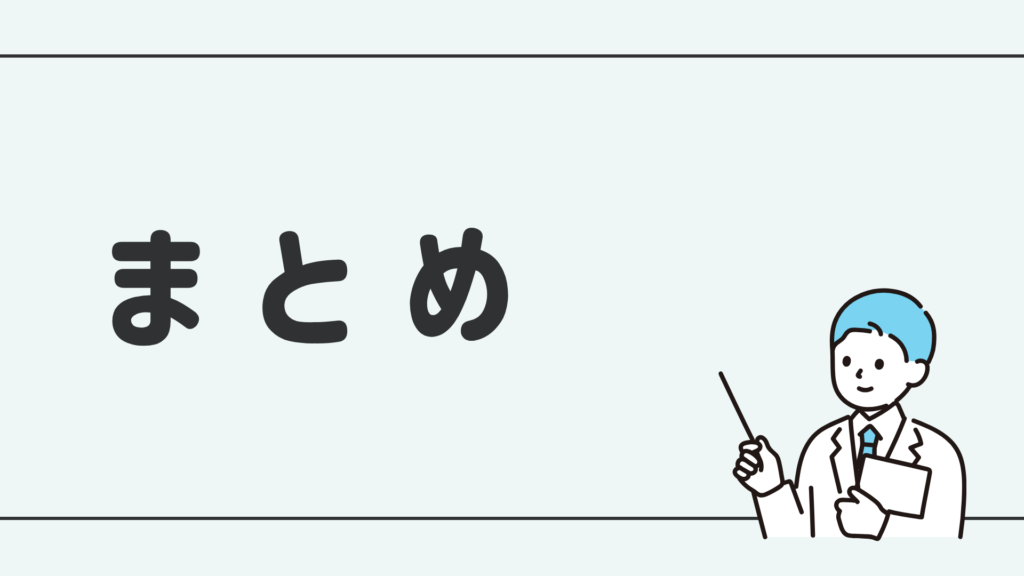
ここまで、個人的な授業づくりのテーマと具体的な工夫についてご紹介させていただきました。
これには先生方それぞれの考え方があるものですし、教科によっても変わると思います。
ただ、今後私がこのブログを通じて数学の授業について発信する際、その根底にはこうした考え方があるのだと知っていただきたく、今回まとめさせていただきました。
何かひとつでも、先生方の授業づくりにおいてご参考になれるものがあれば幸いです。

今回は以上です!お疲れさまでしたっ!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
日々走り続ける全国の先生方へ、敬意を込めて。
※今回の付録シートは下の【PDF資料】ボタンからダウンロードしてください。
↑クリック
【 各学年の授業案リンク 】