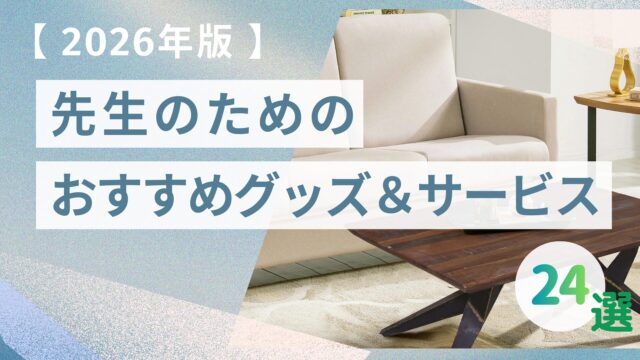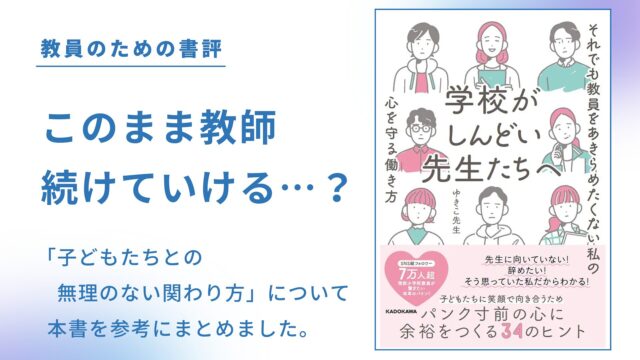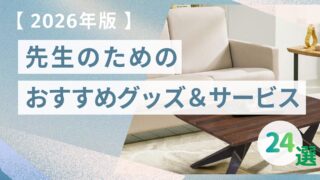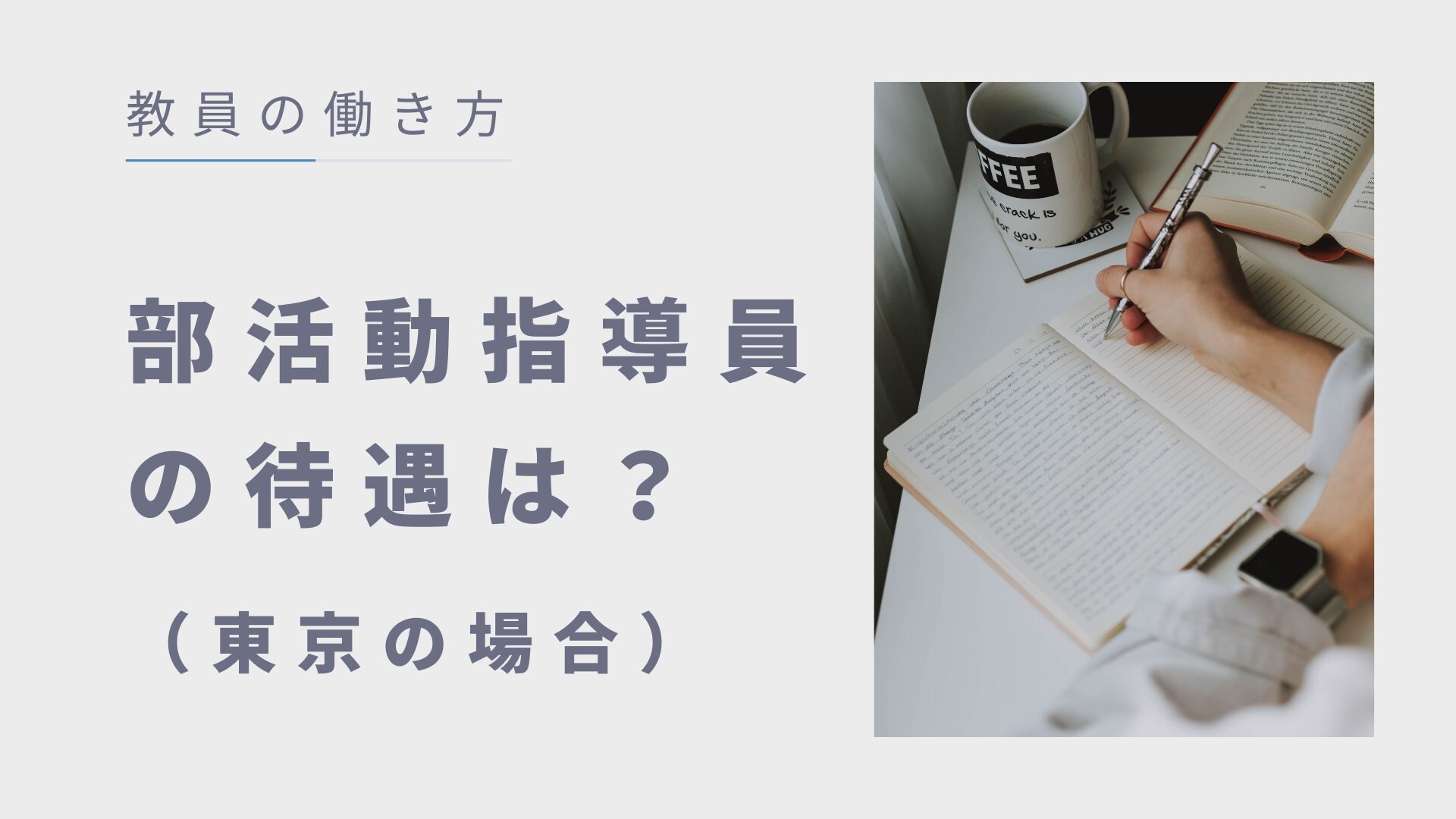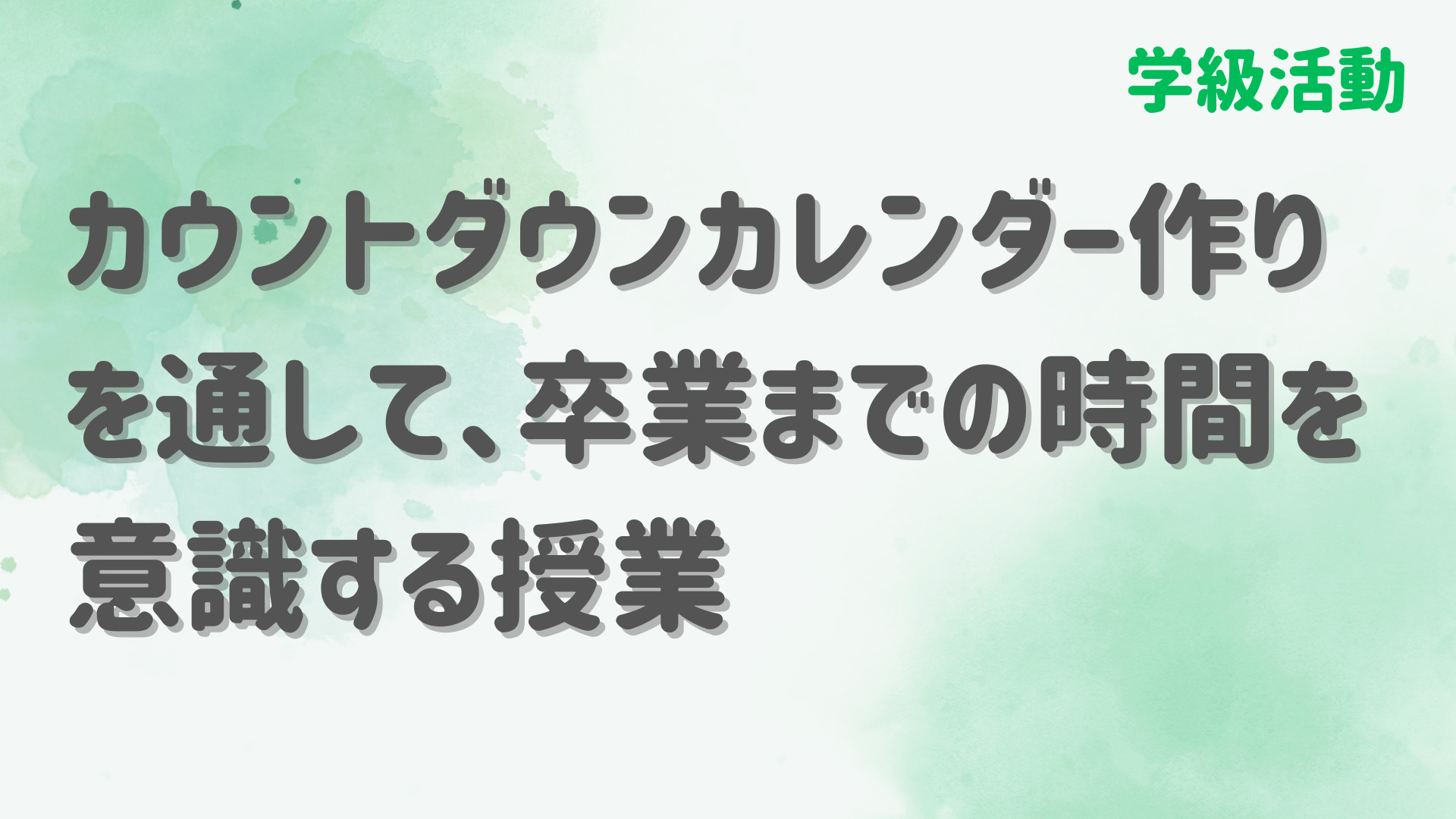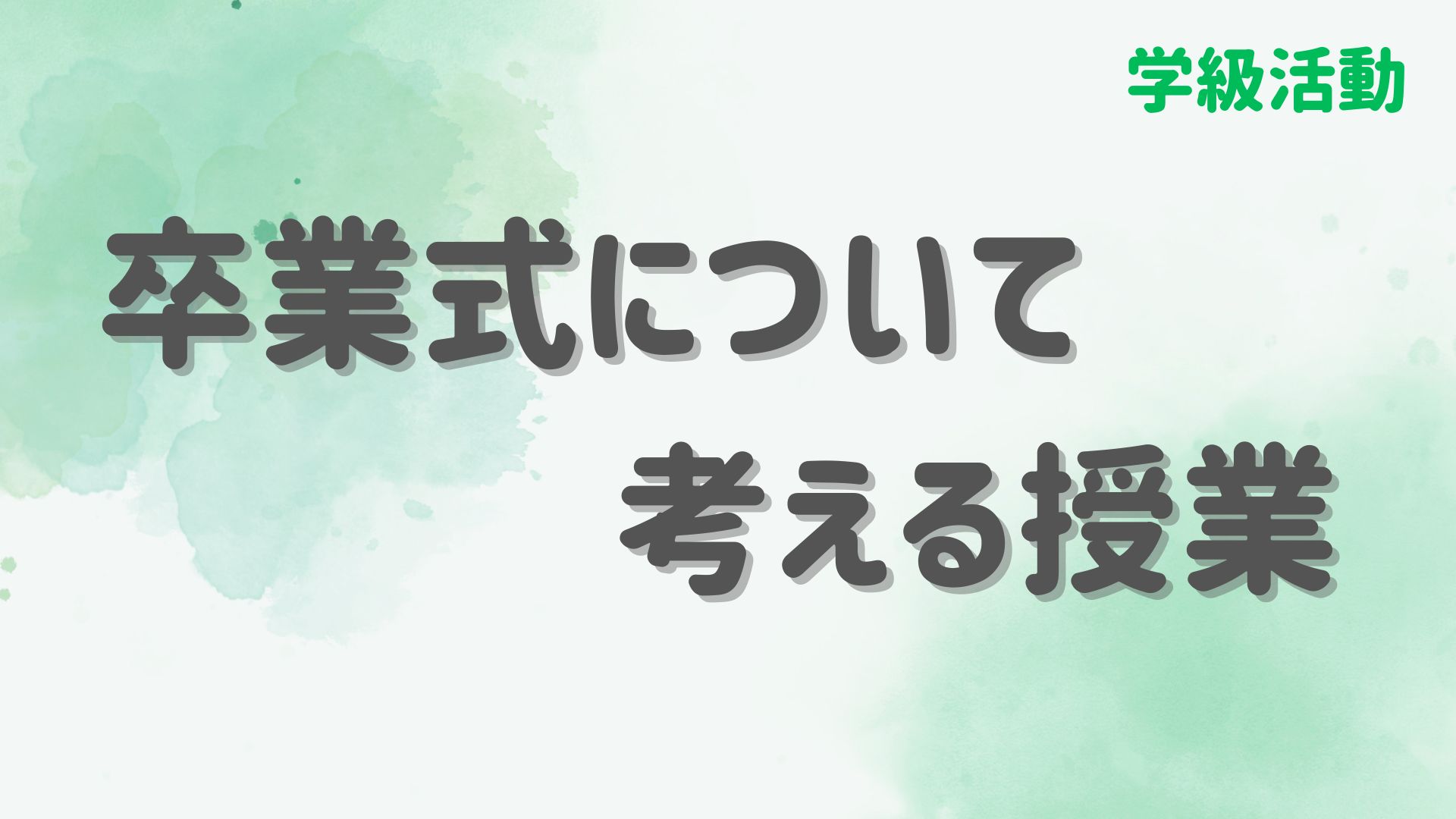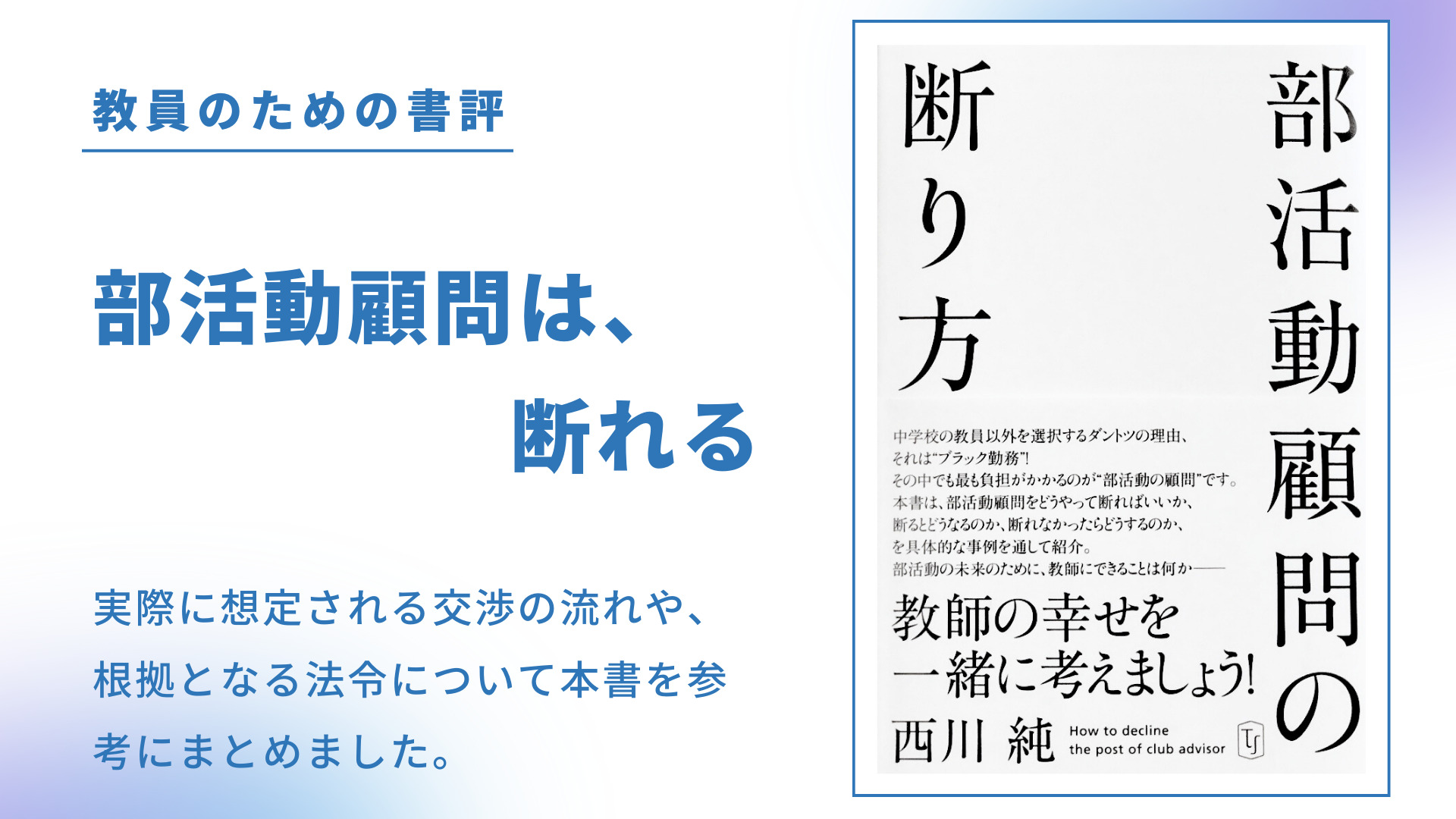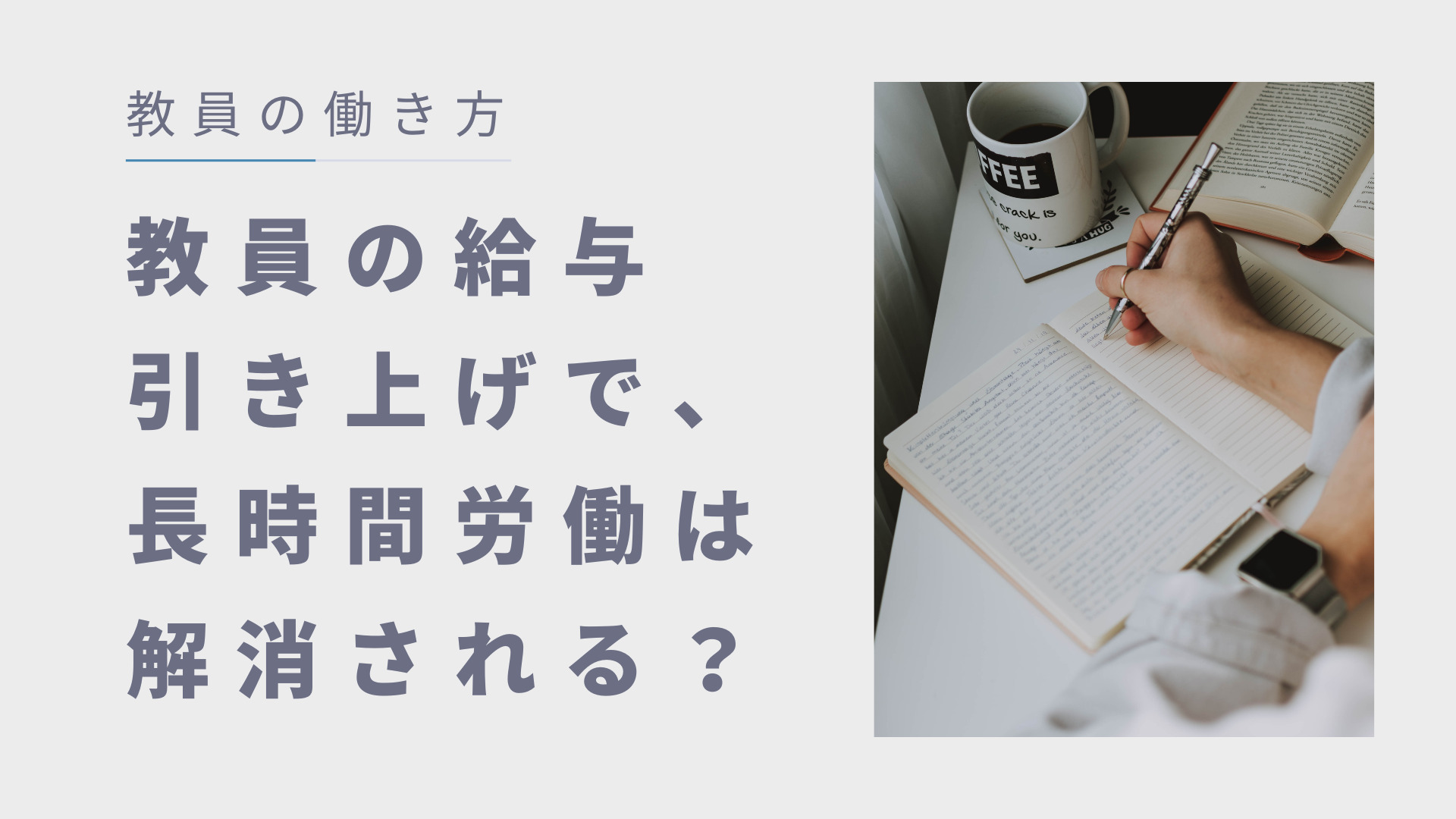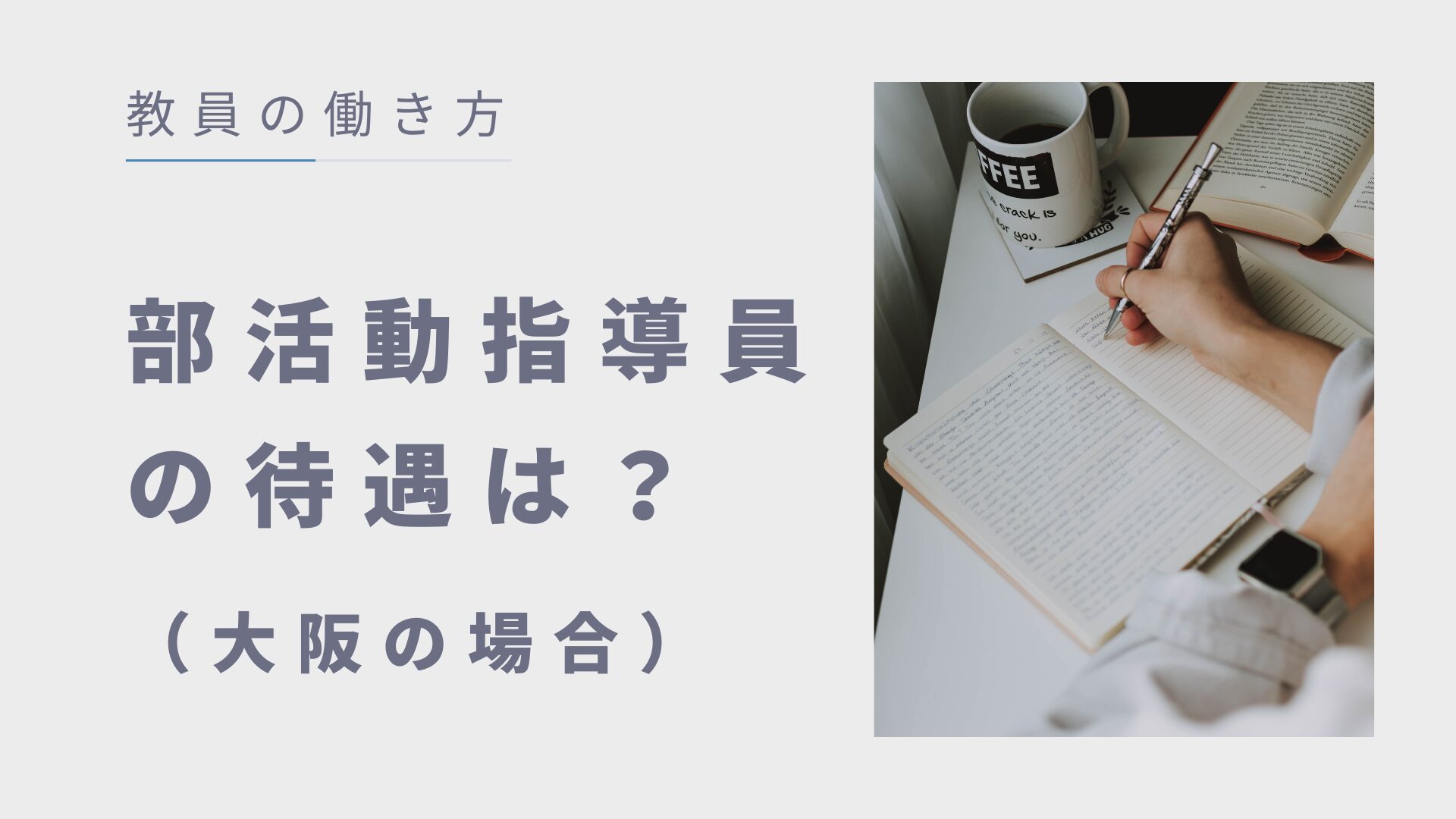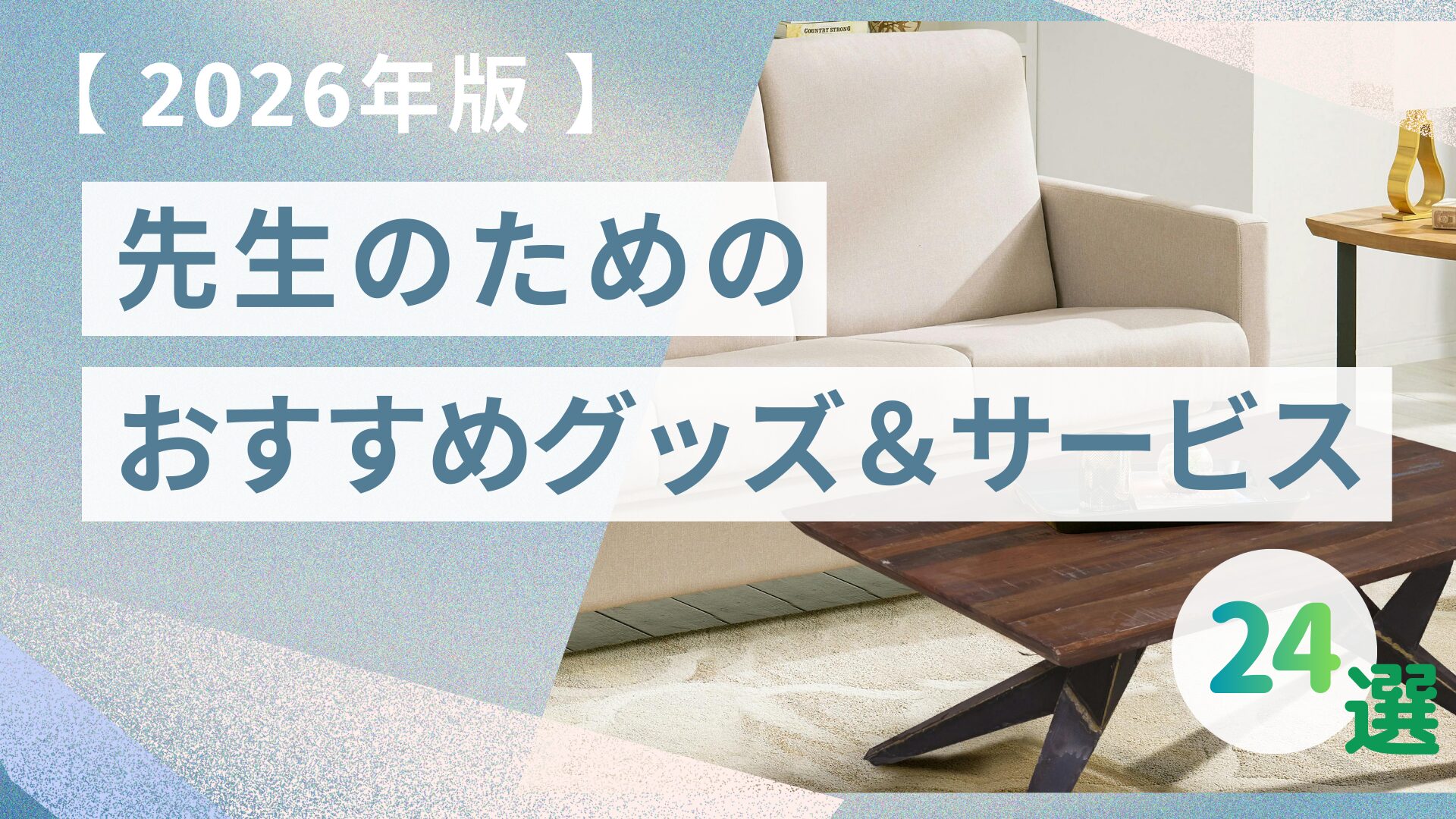【学級開き】トラブルが起きにくい学級をつくる3つのルール(ポイントまとめシート付き)

新学期早々に行われるオリエンテーション。
そこで学級のルールについて考える時間があると思います。
この「ルールづくり」。
生徒主体で進めていくのが理想ではありますが、
そうなると、どうしてもルール自体が抽象的で、判断基準が曖昧なものになりがちです。
その結果、「せっかく話し合いで決めたルールが、結局形だけになってしまった…」なんてこともよくあります。

本人経験談です。
どんなルールを設定し、どこまで生徒たちに落とし込めるかで
その後1年間の学級運営(生徒指導にかける時間と労力)に大きな差が出ます。
そこで今回は、教員側から学級のルールを提示するという前提で
私自身の失敗と試行錯誤からたどり着いた
「1年間、学級を安定して運営するために効果的だったルール」を3つに絞ってご紹介しようと思います。
そして、それぞれのルールにどんな意図があるのか、どんなふうに伝えればいいのかについても、あわせてお伝えしていきます。
- 「せっかくルールをつくったのに、あまり機能していない…」
- 「どんなルールにすれば、学級経営がうまくいくんだろう?」
そんな悩みを抱える先生方の一助となることを願って、本記事が学級づくりの出発点に寄り添う参考資料になれば幸いです。

トラブルが起きたらその時に指導すればいいんじゃないの?

もちろん臨機応変な対応は大事。
でもあらかじめ「1年間これは守ろう!」というルールを明確にすることで、トラブルの予防に繋がると思うよ。
※ご紹介しますのは個人の実践に基づく見解ですので、予めご了承ください。少しでも先生方のご参考になれば幸いです。
今回ご紹介する「3つのルール」についてまとめたPDF資料を、ページ下部にご用意しました。
ぜひダウンロードしてご活用ください。
ルールの決め方について
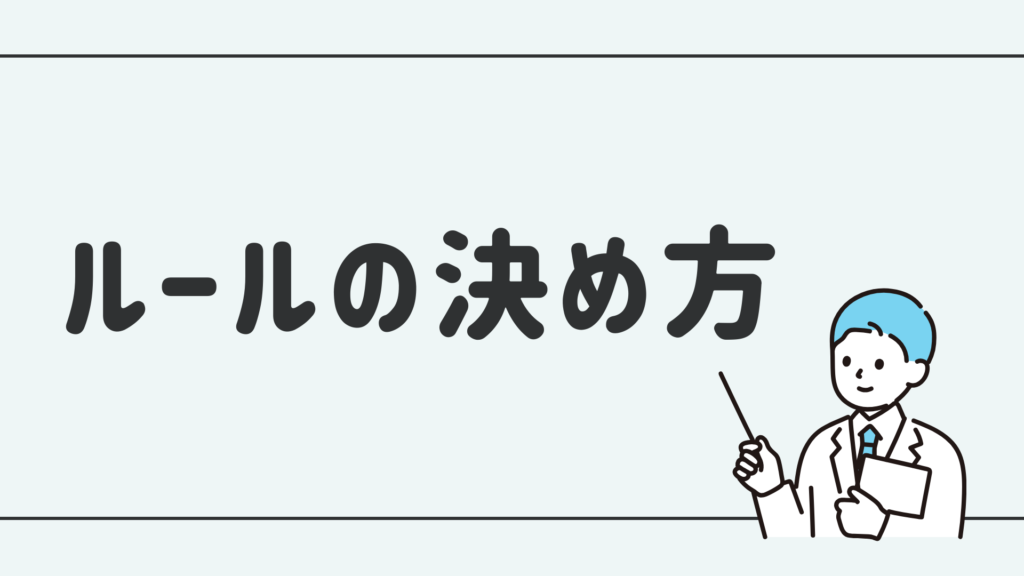
今回ご紹介するルールは、細分化された個別的なものではなく、その大元になる学級運営の大原則のようなもので、私はそれを『学級訓』と呼んでいます。
私の場合、学級訓は「自分が1年間、生徒に徹底させられるものを3つまで」と決めています。
数が多いと私自身が把握しきれず、それによって指導に抜けが生じると、生徒のルールに対する意識が低くなってしまうと考えるからです。
なので「これだけは絶対守らせる!!」というものを3つまでにしぼり、生徒も暗記できるぐらい分かりやすくまとめることを意識します。
ルールの決め方については、生徒同士の話し合いによって決めるという方法もありますが、ここで示すルールは学級運営の根幹を成すものなので、あらかじめ担任が決めた方がよいと思います。
当然これから生活する上でより細かなルールは必要になってきますが、特に担任が重視していることとして学期始めに生徒へ示します。
おすすめしたい3つのルール
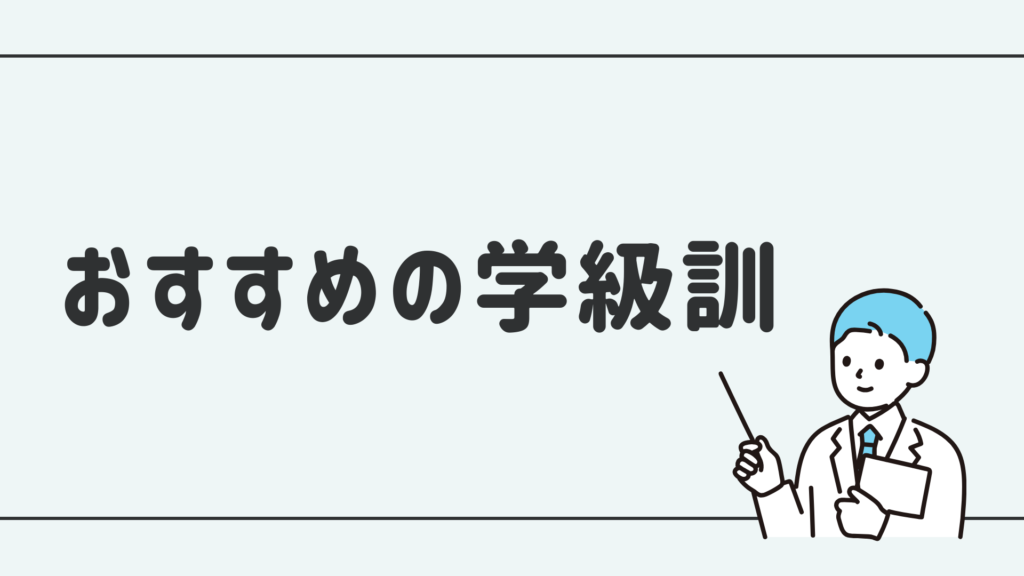
- いじめをしない、させない、見逃さない
- 自分の仕事を完璧にやり通す
- 掃除、整理整頓の徹底
これまで何度も改良し、最終的にこの3つに落ち着きました。
生徒に示した以上、妥協せず、最後まで徹底させることが重要です。
そうした意味で「友達と協力する」や「ことわざ」などのように、できたかできなかったかの基準があいまいになりやすいものや
結果が他者に左右されるものについては除き、個人が集団のために努力すべき最低限の事項を示すことにこだわりました。
いじめをしない、させない、見逃さない
基本的にはそのままですが、「いじめを見逃さない」には
- 嫌な気持ちを我慢しない
- いじめを見つけたら大人に相談する
という意味が込められています。
担任として「絶対にいじめは認めない」という強固な姿勢を示すとともに、もしいじめが発生した場合の具体的な対応についても説明します。

私はあえて、実際にいじめが起きた場面を生徒がリアルにイメージできるように、その学校で定められている対応の手順について時間をとって丁寧に説明するようにしています。
またその際、以下の内容もあわせて全体に伝えていきます。
- いじめを受けた本人はもちろん、そうした状況を教えてくれた人も徹底して守ること
- そのために、いじめは担任だけでなくその他の教員や保護者も含めたチームで対応すること
- 対応については、いじめを受けた人の希望をしっかり聞きながら相談して決め、担任の判断だけで勝手に行動しないこと
学級開きという1年間の土台を作るこの機会に、あらためて「いじめ」についてクラス全体で考え
普段からいじめが起きにくい環境をつくること、いじめを許さない雰囲気をつくることの大切さを真剣に伝えます。
そして、その達成のためには【クラス全員の協力が必要】であることも強く訴えます。

どんなに難しくても、「このクラスならいじめは無くせる」と
担任だからこそ最後まで信じ抜きたいです。
自分の仕事を完璧にやり通す
仕事には係や委員会の仕事だけでなく、日直や給食当番、提出物の期日を守ることも含まれます。
特に提出物に関しては、受験時の書類などを引き合いに出し
期日を守らないと周囲に大きな迷惑をかけたり、自分自身の信用を失墜させたりする危険性があることを強く伝えます。
私は提出物について
- できる限り期日の1日前に提出すること
→期日に欠席したり、書類に不備があったりした時のため - 提出前に不備が無いか生徒自身で最終チェックをすること
→親まかせにしない - もし忘れた場合はいつまでに提出するのか自分から言うこと
→基本的に次の日の朝一で職員室に持ってくる
以上を徹底させています。
提出物を期限までに出せないことが続く場合、保護者連絡もします。
それだけ期日を守り、計画的に行動することが重要だと考えているからです。
もちろん係や委員会の仕事、当番活動も徹底させます。
個人が責任持って自分の仕事を全うすることで、集団生活はより快適なものになります。
自分の仕事をやり抜くことを通して、全員がクラスにとって必要な人になってほしいと願っています。
※係・委員会担当者の決め方については別記事にてまとめましたので、下のリンクよりあわせてご覧ください。

掃除、整理整頓の徹底
キーワードは、「全員で協力し・すばやく・丁寧に」です。
「自分の仕事を完璧にやり通す」と共通する部分がありますが、特に掃除に関しては気が緩みやすく、生徒の精神安定上重要なものなので、あえて分けて示しました。

たしかに、物が散乱している教室では落ち着いて生活ができないよね。
また、ロッカーの中を整理整頓する、床に物を置かないなど
普段から「教室は自分だけのスペースではない」「常に物や場所を誰かと共有している」という他者への意識を持たせることで、いじめの防止にもつながっていくと考えています。

私の場合、ロッカー内の整理整頓を徹底させるために、すべての生徒にブックスタンドを持参してもらっています。
まとめ
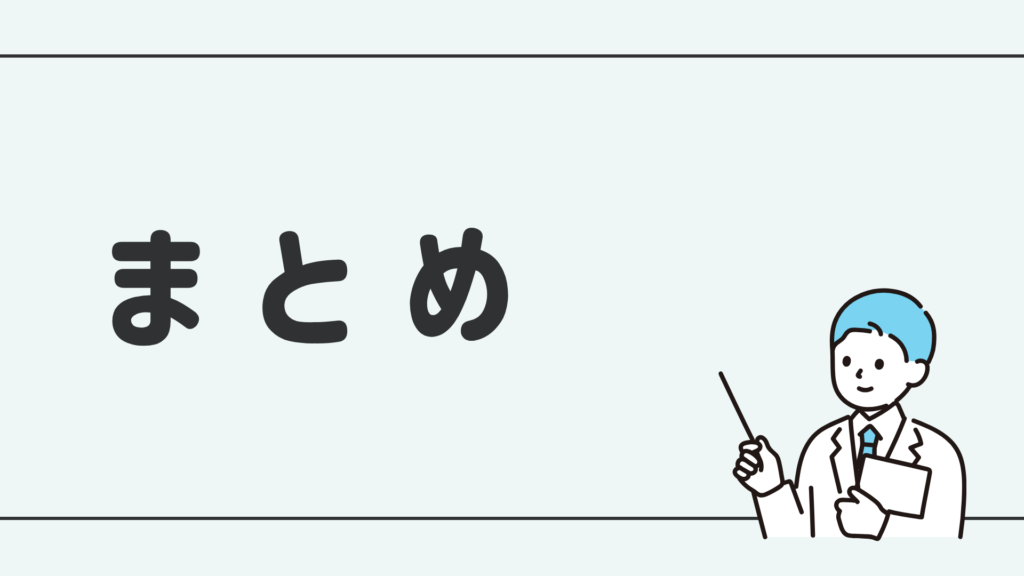
ここまで、私が学級開きの際に生徒へ示している
学級運営の大原則「学級訓」についてまとめさせていただきました。
集団のルールは、初めにゆるく設定し、徐々に厳しくしていくというやり方だと
生徒は不満を感じやすくなるそうです。(Q-Uの講習会で学びました)
この先1年間の安定した学級運営を実現させるため、綿密な準備のもと、学級開きという最大のチャンスを生かしていきたいです。
また、大切なのはルールを作ることではなく、作ったルールを全員に守らせることです。
そのためにも思いを込めた学級訓を設定し、常に生徒の目に入る位置に大きく掲げ、日々粘り強く指導していくことが必要だと思っています。

今回は以上です!お疲れさまでしたっ!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
日々走り続ける全国の先生方へ、敬意を込めて。
※今回の付録シートは下の【PDF資料】ボタンからダウンロードしてください。
↑クリック