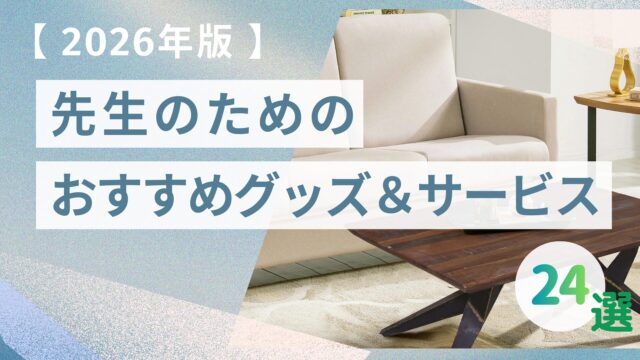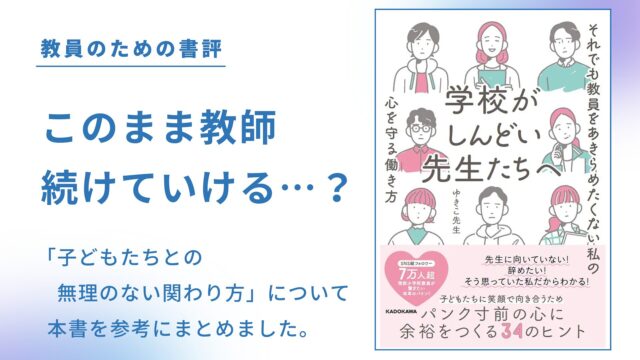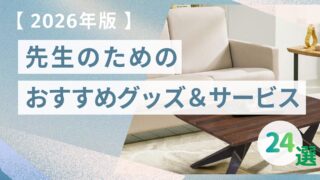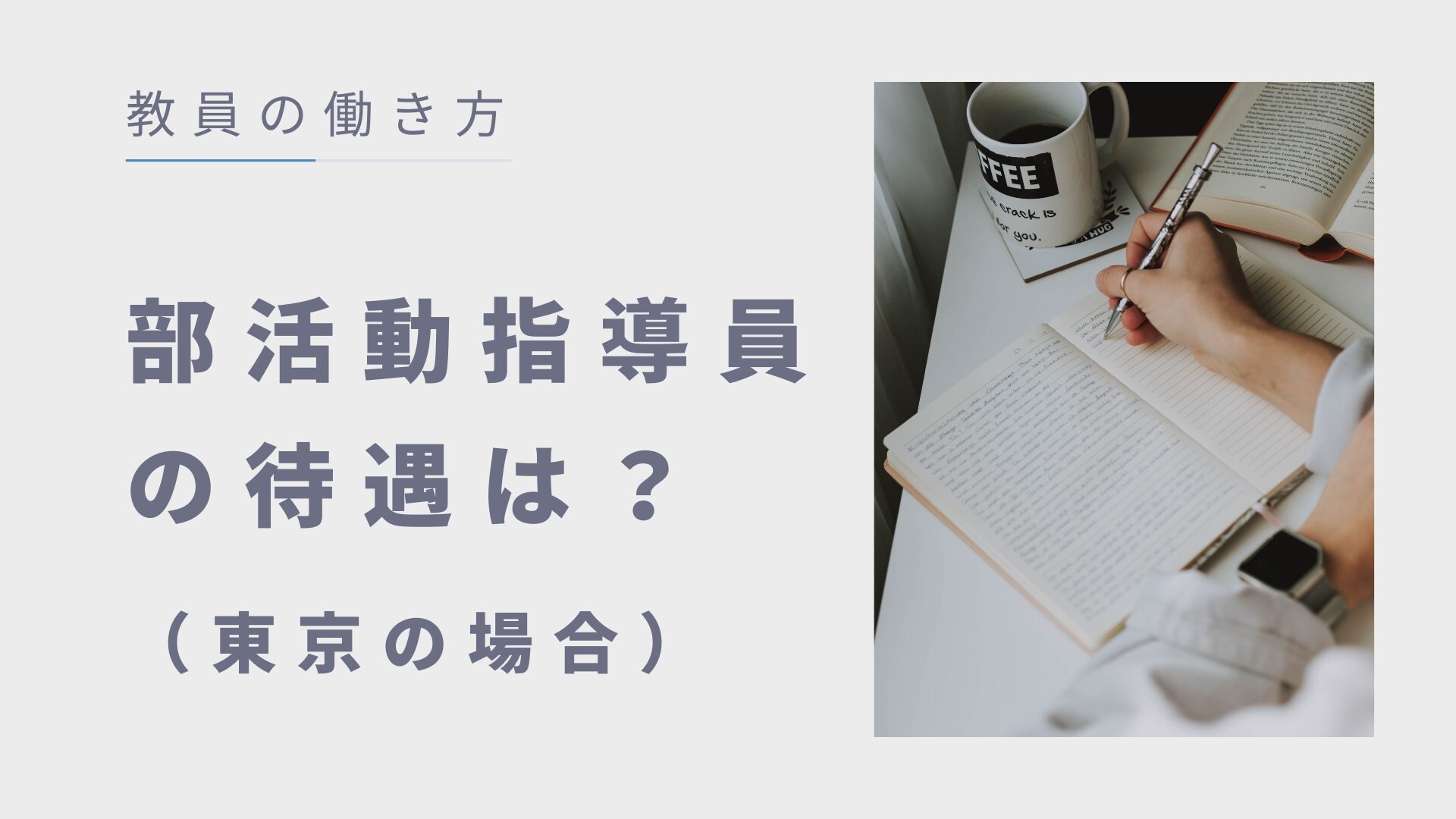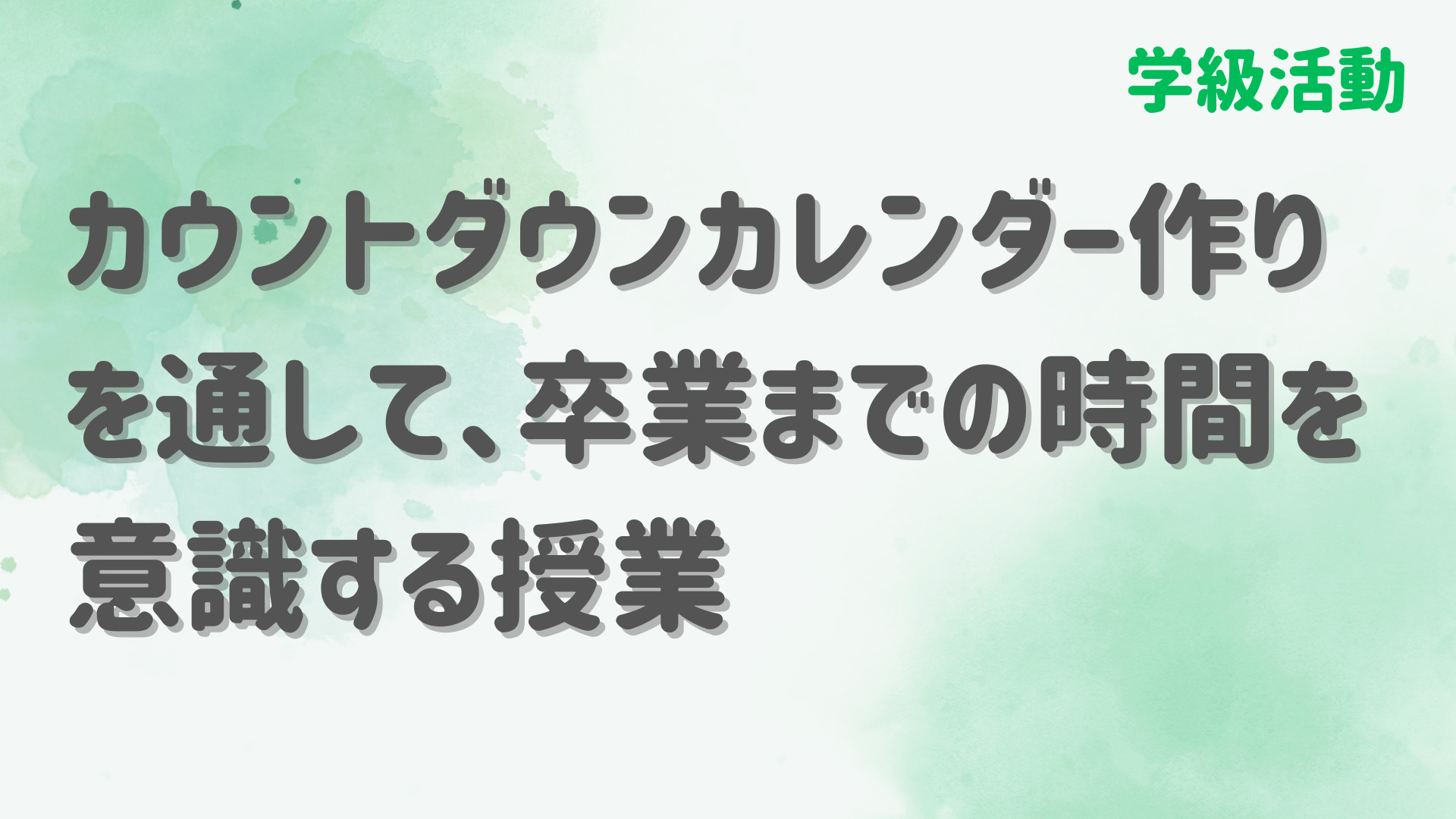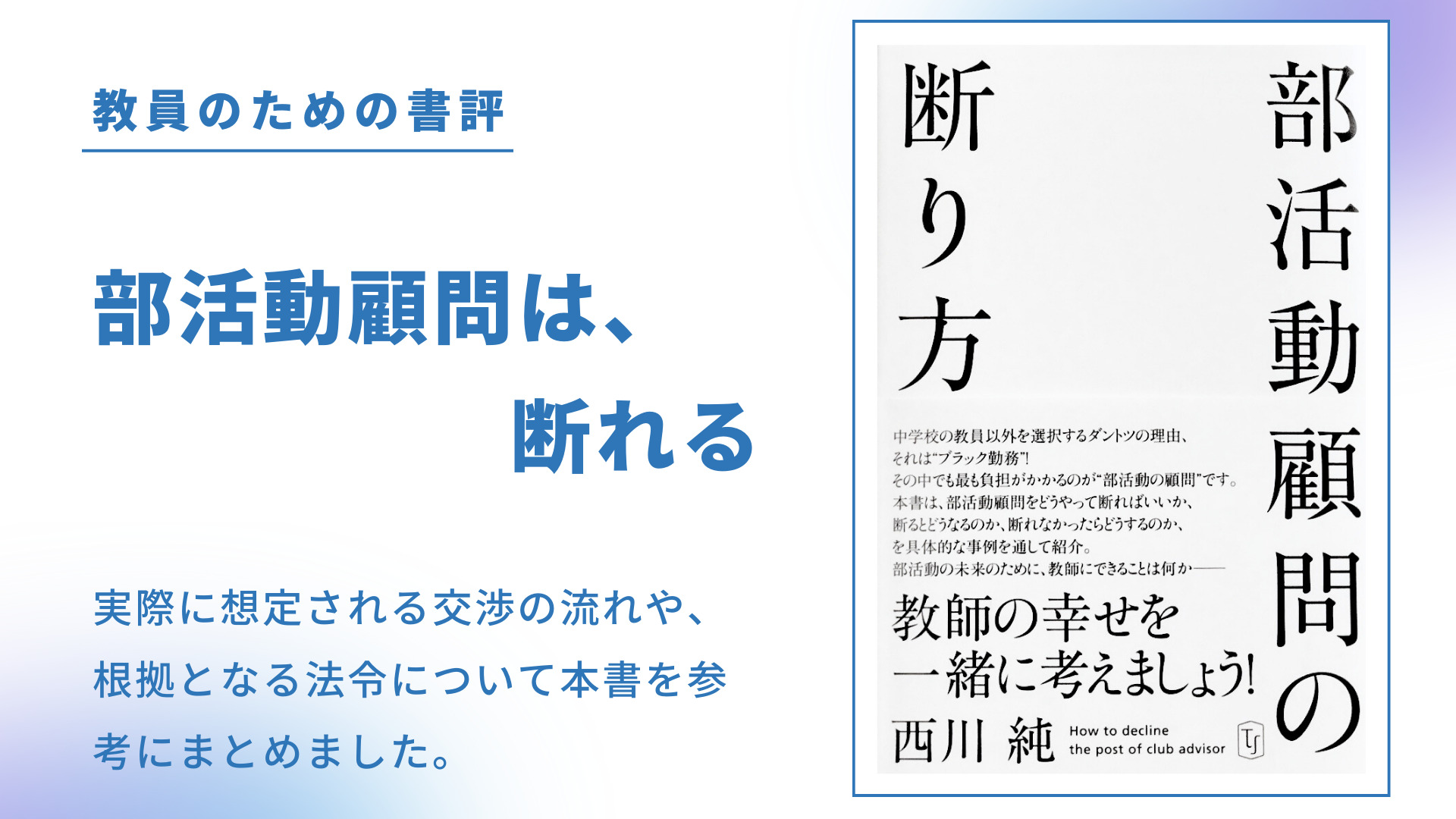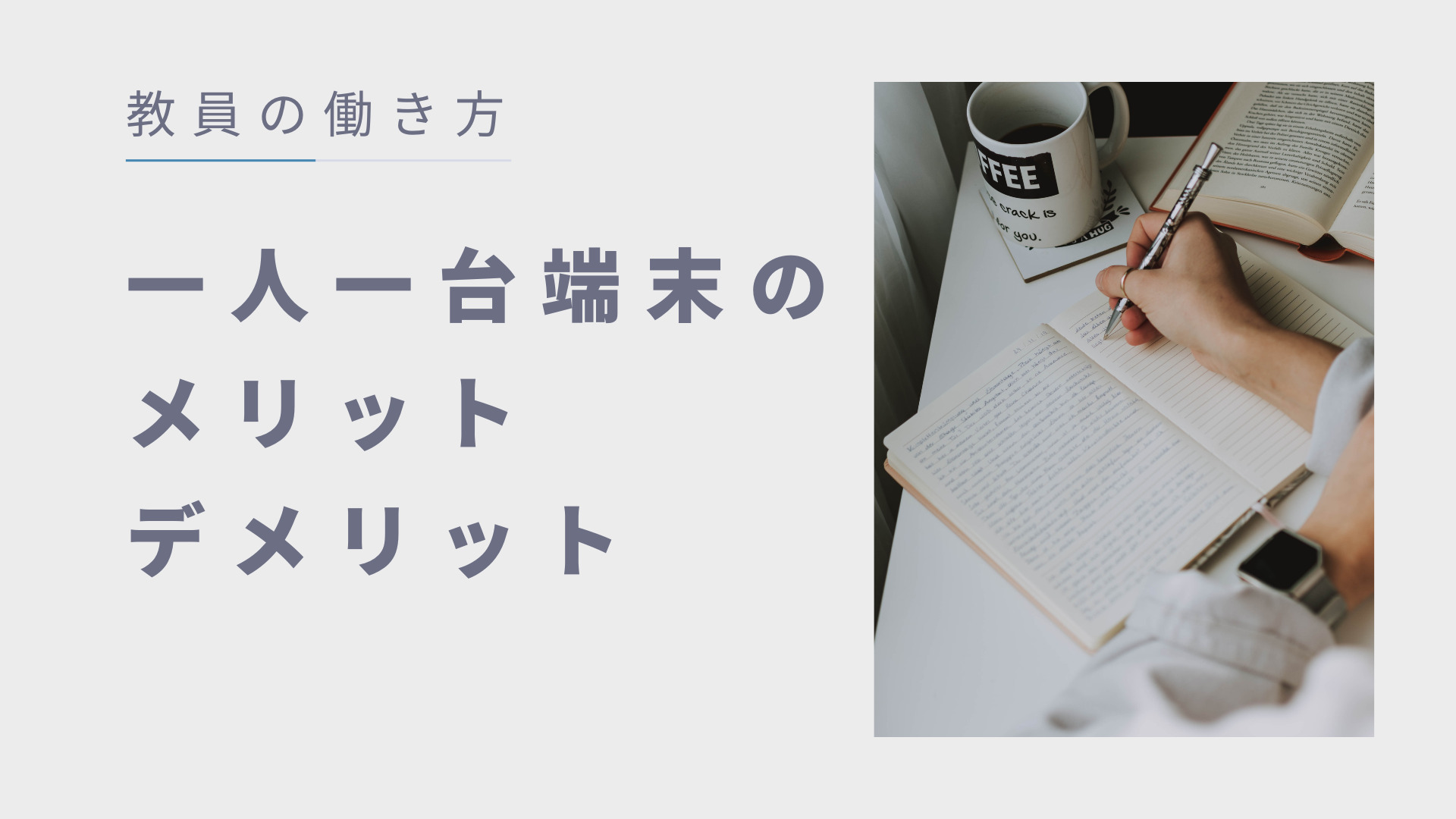もう迷わない!保護者の心をつかむ学級懇談会の進め方【準備編】(生徒用アンケート付き)

授業参観後に学級懇談会を開く学校は多いと思います。
学級懇談会は学年懇談会とは違って担任の果たす役割が大きいため、特に初任の先生は不安を感じやすいところです。
そうした不安を減らして当日の会をスムーズに進行していくためには
環境の整備、学級の現状把握、伝えることの精選、効果的な伝え方の検討…など、事前の準備が欠かせません。
そこで今回は「学級懇談会を充実させる具体的な準備」をテーマに、上記のような、懇談会を運営する上で外せないいくつかのポイントについて、それぞれ実用的なアイデアを提示しながら詳細にまとめて解説したいと思います。

学級懇談会ってどう立ち振る舞えばいいのか、イマイチよくわからない…。

やるべきことを精査して準備することで、当日あたふたせず、気持ちに余裕を持って進行できるようになるよ!
※ご紹介しますのは個人の実践に基づく見解ですので、予めご了承ください。少しでも先生方のご参考になれば幸いです。
今回の付録である【生徒アンケート】は、PDF資料としてページ下部にご用意しました。
ぜひダウンロードしてご活用ください。
学級懇談会を開く目的(目指すゴール)
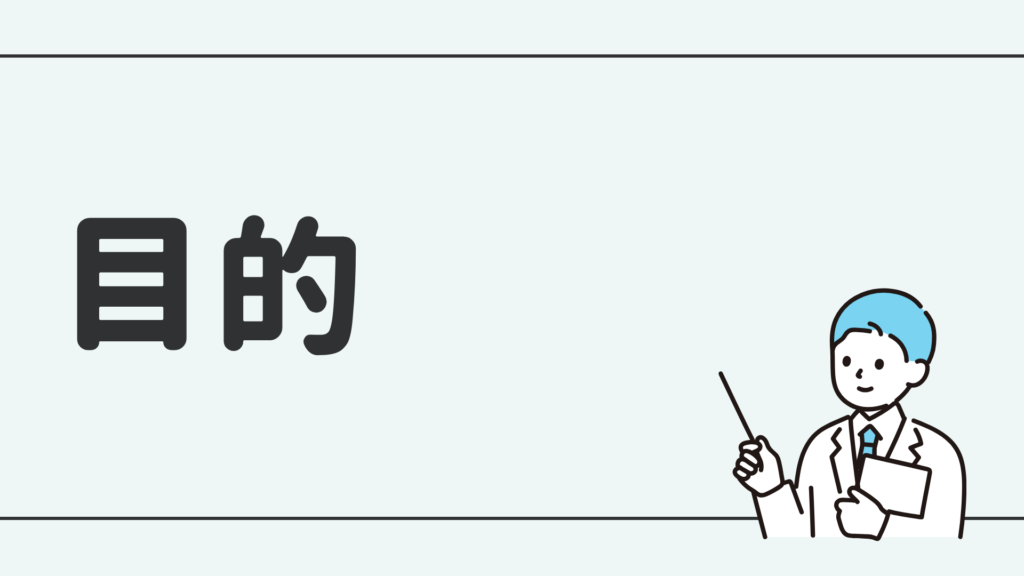
学級懇談会を開く目的は、大きく分けて以下の3つがあると考えています。
学級の雰囲気やそこで生活する生徒の様子を保護者に伝える
( 担任 ⇒ 保護者 )
今後の指導方針を共有して担任と保護者の協力体制を構築する
( 担任 ⇔ 保護者 )
懇談を通して保護者同士の交流を深める
( 保護者 ⇔ 保護者 )
学級懇談会は個別の保護者面談とは異なり、特定の生徒個人について情報交換するのではなく、学級全体についての話題を主として扱います。
また説明会ではなく懇談会であることから、担任が一方的に話をするのではなく、全員参加型でトークを展開することも大きな特徴のひとつです。

気づいたら担任だけがしゃべっていたってことあるよね。

わかるわー。
やはり参加してくださった方には最低でも一人一言は必ずお話する機会を設けたいですし、理想としては懇談会が終わった後に保護者同士の交流が自然と広がっているような状態を目指したいです。
おすすめ準備1:生徒アンケートの実施
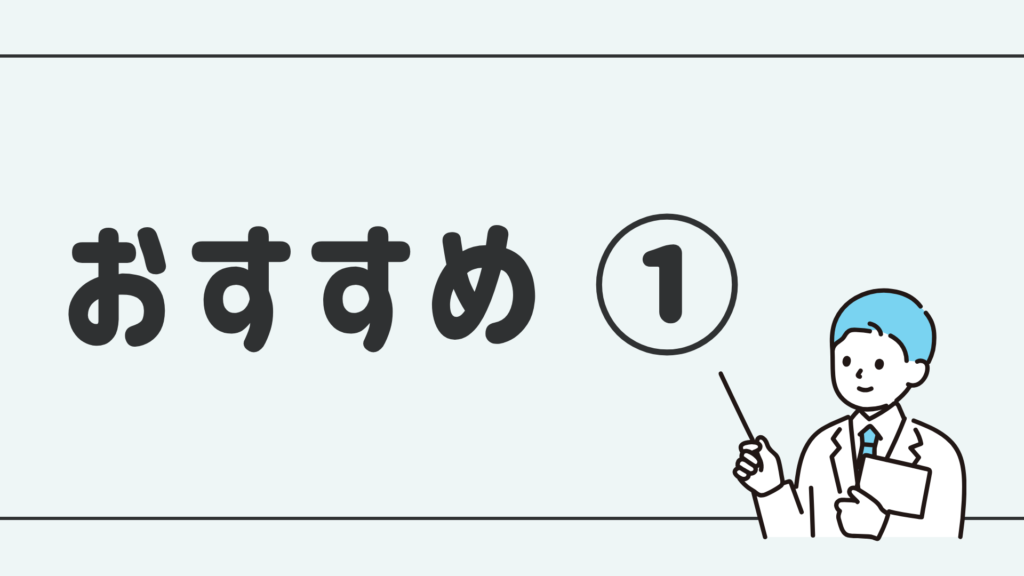
※今回の付録シートはこちらのアンケートになります
(ページ下部の黒板ブロックからダウンロードしてご活用ください)
学級の雰囲気を保護者へ伝えるにあたり、事前に生徒からアンケートで情報を集めておくと便利です。
今回ご用意した生徒アンケートでは、クラスの特徴や授業中の様子をなどを問うベーシックな質問だけでなく、
家庭学習にかける時間やデジタルデバイスを使用している時間、将来について考えていることなど、懇談会で話題にしやすいものもいくつか取り入れました。
このほか「今友達との間で流行っていること」「保護者の方に言われて嬉しかったこと」といった質問も設定しましたが、これらは集計結果をクイズ形式で発表したりすると面白いかもしれません。

学級の雰囲気を伝える際は担任から見たクラスの様子だけでなく、生徒からの視点もバランスよく取り入れながら伝えるのがおすすめです。
おすすめ準備2:スライドショーの作成
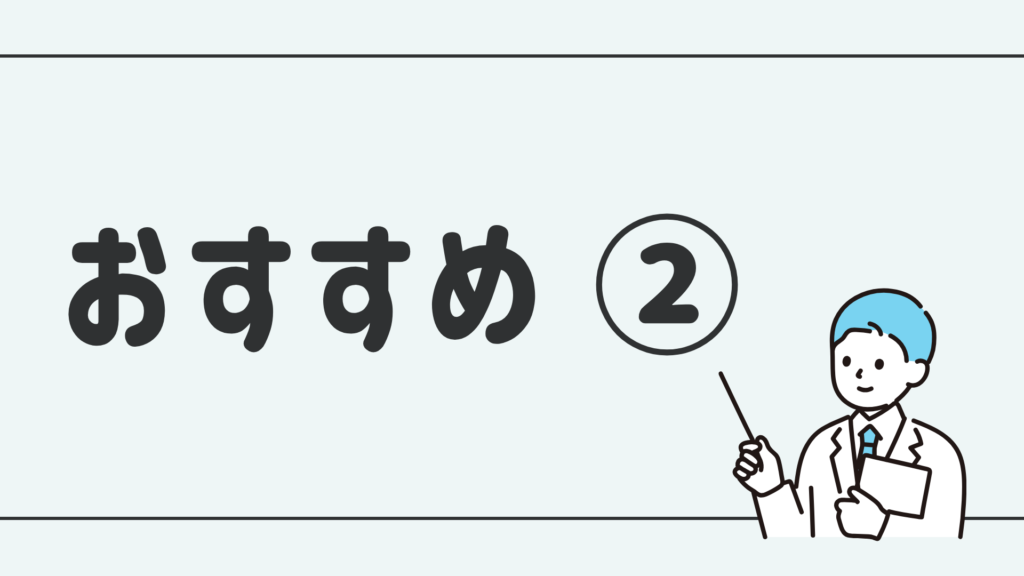
私は懇談会の際、最初にこれまでの写真を音楽付きでまとめたスライドショーを流すようにしています。
やはり言葉だけでは伝えきれないことも多くあり、そうした意味でこのスライドショーは大変有効です。
写真は登場生徒がなるべくかたよらないよう気をつけますが、事前に参加される保護者がわかっている場合は、できるだけそのお子さんがアップで写っている写真を取り入れるようにしていました。
また、写真の選別から学級委員や有志生徒に関わってもらうのもひとつの手だと考えています。
私も実際に生徒と一緒にスライドショーを作って上映したことがありますが、流し終わったあとにそのことを参加された保護者の方へお伝えしたところ、とても好評でした。
iPadなどの学校端末に動画編集用のアプリケーションがあれば、制作の大部分を生徒に任せることができますし、むしろ教員より上手に使いこなす生徒もいたりします。

今の若い子ってすごいですよねぇ~。
おすすめ準備3:掲示物の充実
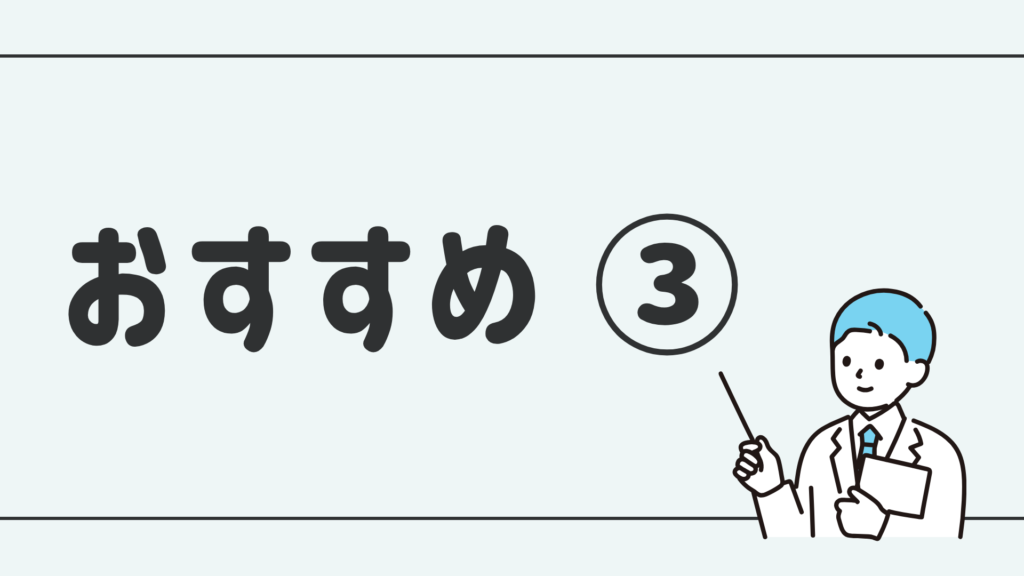
掲示物を充実させることで教室の雰囲気を明るくしたり、生徒が授業でどんなことを学んでいるのかを参観した保護者へダイレクトに伝えたりすることができます。
また懇談会が始まるまでの間や終了後の時間など、保護者がそれを見て交流を深めるきっかけになるかもしれません。
掲示するものとしては
- 学級目標や約束ごとなど、学級の教育方針を示すもの
- スライドショーに載せきれなかった写真
→写真に写りたがらない生徒がいる場合、その生徒が写った写真は掲示しない - 学習の成果物
→授業の課題(ノートのコピーもおすすめ)、美術や技術で制作した作品、学活や総合で使用した資料…など
以上がおすすめです。
ただし準備にかけられる時間には限りがありますし、情報量が多ければいいというわけでもありませんので、あくまで参考程度に留めていただければと思います。
おすすめ準備4:伝えることリストの整理
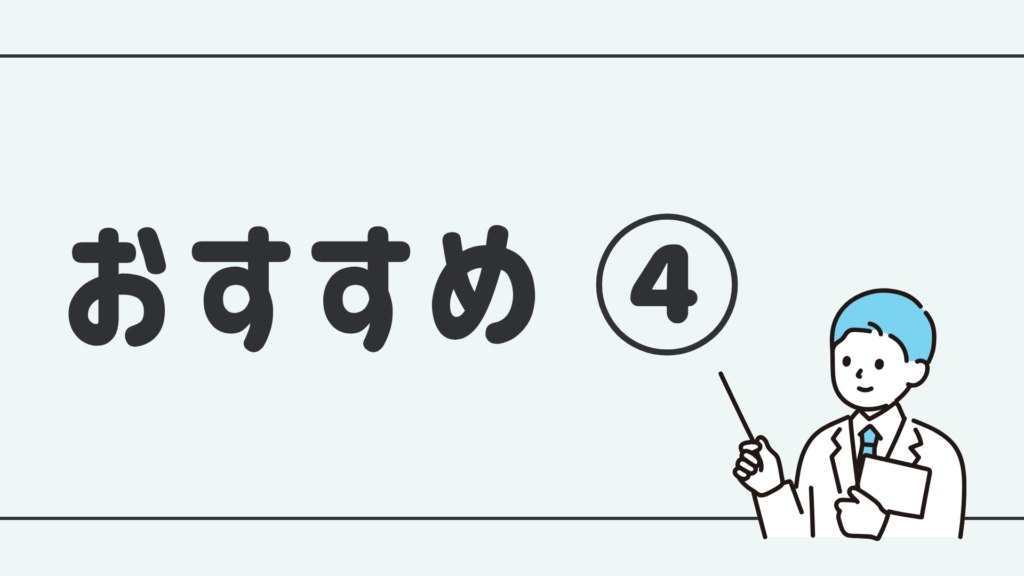
参加された保護者の方へ学級の様子をお伝えする際など、担任から何かを説明したり、情報を提供したりする場面は少なからずあります。
そうしたとき担任の話がややこしかったり、だらだら一人でしゃべり続けてしまったりすると、伝えたいことが伝わらないどころか保護者に不信感を与え、その後の教育活動に支障が出てしまうリスクもあります。
そうした意味で、①そもそも懇談会で何を伝えたいのかと、②どのように伝えればわかりやすいのかの2点について事前に十分検討し、カンペとしてまとめておくことをおすすめします。
伝えることの例としては
- はじめのあいさつ
- 普段学校の教育活動にご理解をいただいていることへの感謝
→学級懇談会に参加していただいたことへの感謝も忘れない - 担任自己紹介
- 学級懇談会を開く目的について
- 学級目標や約束ごとなどを含めた学級経営の方針について
- これまでの生活面と学習面それぞれの様子について
→各種振り返り、生徒アンケート、スライドショー、掲示物などと関連づけるとよい - 担任の所感
→学級の様子を見て感じること、指導する上で迷っていることなど
(ポジティブ8割、ネガティブ2割のバランスを意識) - 今後予定されている行事やそれに向けた指導の方針について
- 最新の教育時事や研修などで話題になったこと
→担任の学ぶ姿勢を示すことができる - おわりのあいさつ
などが挙げられると思います。
もちろん、これらすべてを伝えなければならないというわけではなく、担当する学年や懇談会を実施する時期、学級の特性に応じてその内容を精査することが必要です。

ここで伝えたいことをまとめておくと、その後の学級通信にも活用できそうだね。
※学級懇談会当日の進行については別記事にてまとめましたので、下のリンクよりあわせてご覧ください。

おすすめ準備5:学級通信の活用

学級懇談会をより充実させるために、学級通信を活用することは有効です。
考えられる主な活用方法としては
- 学級懇談会開催のお知らせ
- 懇談会テーマの事前通知
- 懇談会次第の事前通知
- 事前・事後アンケートの実施
→Googleフォームで作成したアンケートのQRコードを載せるなど - 懇談会参加のお礼と、参加されていない保護者への情報共有
などが挙げられます。
②については、懇談会で話し合う話題や意見をいただきたいことについてあらかじめお知らせしておくことで、保護者側も事前に準備ができますし、その話題に興味を持った方の参加を促すことにもつながります。
③については、参加する保護者に懇談会全体の見通しを持っていただくことができるほか、
同じ学校に兄弟姉妹が在籍している保護者の場合、複数の学級懇談会をハシゴすることがありますが、その際にどの学級から参加していくかを判断する材料にもなります。
その他
懇談会当日、教室の入り口に生徒名の名札を置き、保護者にご自身のお子さんの名札を取って着席してもらうことで、参加している方が誰の保護者なのかを確認しながら懇談会を進めることができるので便利です。
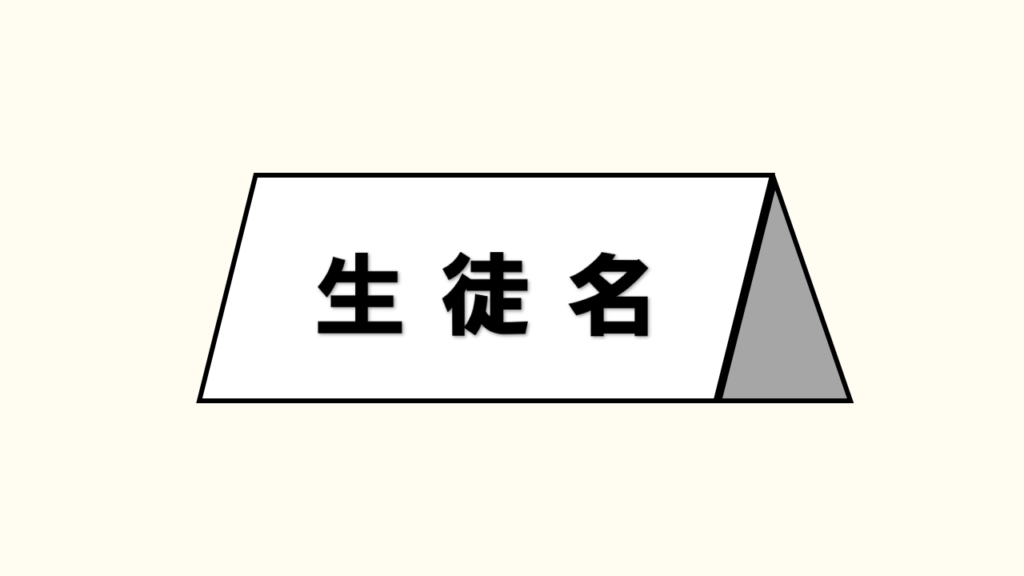

学活の時間などを使って、あえて生徒に手書きで名札を作ってもらうとイイ感じになりますね。

①出席者チェック用の学級名簿、②ペン、③名札、④本日の資料
以上4点セットを教室の入り口にセッティングしよう!
まとめ
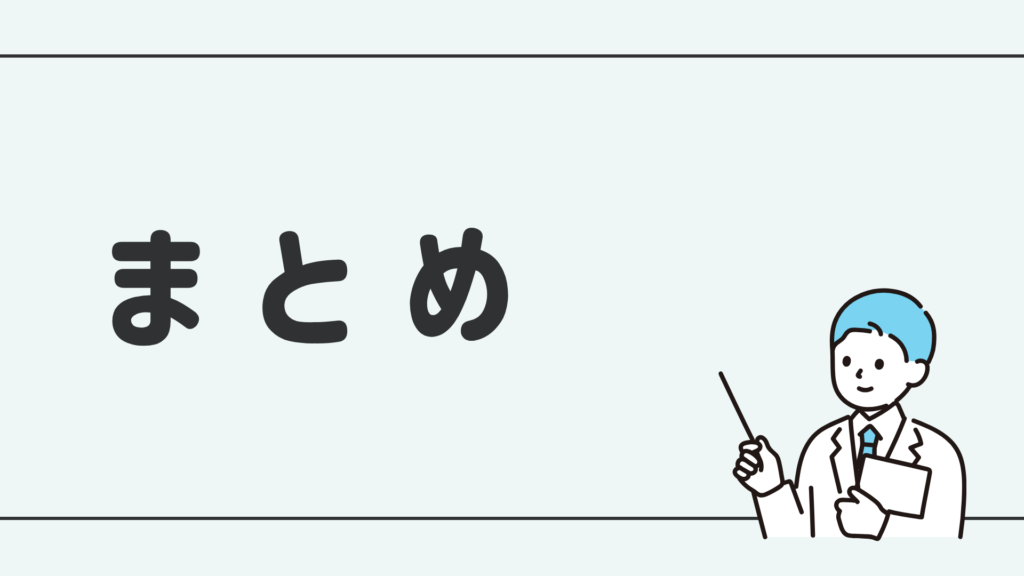
ここまで、学級懇談会に向けたおすすめの準備についてご紹介させていただきました。
日々の業務の合間にこれらを同時並行で進めていくのは大変です。
どうか自分を追い込みすぎることなく、可能な範囲でご参考にしていただければと思います。
学級懇談会に限らず各行事や日々の授業、生徒指導においても、それが成功するかどうかは事前の準備で8割決まると思っています。
忙しい毎日ですができる範囲でコツコツ準備を進め、当日に余裕を持って会を進行できると、保護者もきっと安心してくれるはずです。
最後にもう一度、私が考える「学級懇談会を開く3つの目的」について確認し、まとめとします。
- 学級の雰囲気やそこで生活する生徒の様子を保護者に伝える
( 担任 ⇒ 保護者 ) - 今後の指導方針を共有して担任と保護者の協力体制を構築する
( 担任 ⇔ 保護者 ) - 懇談を通して保護者同士の交流を深める
( 保護者 ⇔ 保護者 )

先生方の普段のがんばりが、しっかり保護者に伝わるよう祈っています!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
日々走り続ける全国の先生方へ、敬意を込めて。
※今回の付録シートは下の【PDF資料】ボタンからダウンロードしてください。
↑クリック